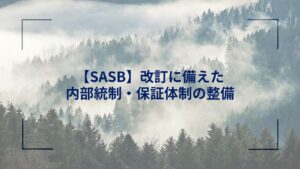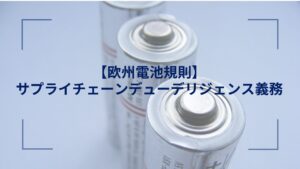温室効果ガス(GHG)排出量データを正確に分析し、各カテゴリの排出源を詳細に把握することは、効果的な削減計画の策定と持続可能な戦略の実現に不可欠です。本記事では、Scope1、Scope2、Scope3のデータ読み取りポイントを中心に、排出量削減に向けた指標の選定方法、進捗管理、データ比較の重要性を解説します。


1.Scope1,2,3におけるデータ読み取りのポイント
温室効果ガス(GHG)の排出量データを正確に読み取ることは、削減計画を効果的に実施するために不可欠です。Scope1、Scope2、Scope3それぞれに固有のデータ収集要件と課題があり、それに応じた方法でデータを管理する必要があります。
2.Scope1のポイント
Scope1は、自社が所有または管理する施設や設備で発生する直接的な排出を指します。
このカテゴリのデータ読み取りには以下のポイントが重要です。
排出源の特定
主要な排出源として、ボイラー、発電機、製造プロセス、企業所有車両などが挙げられます。排出源ごとの使用量を記録し、それぞれの活動に対応する排出係数を適用します。
活動データの収集
燃料使用量(例: 天然ガス、石油、石炭)を正確に測定します。
使用量データは請求書や直接測定装置を基に収集することが一般的です。
排出係数の適用
国や地域ごとに提供される排出係数(例: 環境省データベース)を利用します。
燃料の種類や消費量を詳細に把握し、データの信頼性を確保する必要があある為、一部のプロセスでは排出が多様で、データ収集が煩雑になる場合があります。
3.Scope2のポイント
Scope2は、購入した電力、蒸気、熱、冷却エネルギーの使用に伴う排出を対象とします。このカテゴリは企業のエネルギー使用効率と密接に関連しています。
購入エネルギーの特定
消費エネルギーの種類(例: 電力、蒸気、冷却水)を明確にします。
エネルギー供給者から提供される請求書や契約データが主な情報源となります。
供給元データの使用
電力供給者が発表する排出係数を使用します。
再生可能エネルギーを活用している場合は、グリーン電力証書や購入契約書をデータとして記録します。
複数拠点で異なる供給元からエネルギーを購入している場合、それぞれのデータを統合する必要があります。電力の供給元が明確でない場合、平均的な排出係数を用いることで精度が低下する可能性があります。
4.Scope3のポイント
Scope3は、サプライチェーン全体の活動に関連する間接排出を包括します。このカテゴリはさらに15の細分化された項目を持ち、最も包括的かつ複雑なカテゴリです。各カテゴリーごとに排出係数の適用は公開されているもの(例: 環境省データベース)を利用しますが、1次データ(サプライヤー算定結果)が取れるものもあります。
1.購入した製品・サービス
概要: 自社が調達した原材料や外部サービスの生産に伴う排出量。
活動量の収集: サプライヤーからのLCAデータや購入量情報を取得する。
課題: サプライヤーの規模や地域によりデータ精度が異なる。
2. 資本財
概要: 資本財(工場、設備など)の建設・製造に伴う排出量。
活動量の収集: 投資額データと資本財ライフサイクル情報を収集。
課題: 長期使用資産の排出量を正確に把握するためには、詳細なライフサイクルデータが必要。
3. 燃料およびエネルギー活動(Scope 1, 2に含まれないもの)
概要: 燃料や電力の生産、供給に伴う排出量。
活動量の収集: 燃料供給者から生産・輸送データを取得。
課題: サプライチェーン上流でのデータ収集が困難。
4. 輸送および配送(上流)
概要: 原材料や部品の物流に伴う排出量。
活動量の収集: 輸送距離と重量を物流業者から取得。
課題: サプライチェーン全体のデータ統合が必要。
5. 廃棄物(事業活動から出るもの)
概要: 自社の事業活動で発生した廃棄物の処理に伴う排出量。
活動量の収集: 廃棄物処理業者からのデータを取得。
課題: 廃棄物の不適切な処理によるデータ不足。
6. 従業員の出張
概要: 業務目的での従業員の移動による排出量。
活動量の収集: 出張頻度や距離データを取得。
課題: 従業員間での移動手段の多様性に対応する必要あり。
7. 従業員の通勤
概要: 従業員の職場通勤に伴う排出量。
活動量の収集: 通勤距離、回数を従業員調査で取得。
課題: 統一的なデータ収集が難しい。
8. リース資産(上流)
概要: 自社がリース契約している資産の使用に伴う排出量。
活動量の収集: リース提供者からエネルギーデータを収集。
課題: 提供者からのデータ取得にタイムラグが生じる可能性。
9. 輸送および配送(下流)
概要: 製品を顧客に届ける物流活動に伴う排出量。
活動量の収集: 出荷量と輸送距離を物流業者から取得。
課題: 輸送業者ごとのデータばらつきに対応。
10. 販売した製品の加工
概要: 販売された製品が顧客によって加工される際の排出量。
活動量の収集: 加工業者からエネルギー使用データを収集。
課題: 加工業者のデータ提供が遅れる可能性。
11. 販売した製品の使用
概要: 販売された製品の使用に伴う排出量。
活動量の収集: 製品の平均エネルギー消費データを調査。
課題: ライフサイクル全体での使用パターンを特定する難しさ。
12. 販売した製品の廃棄
概要: 製品が廃棄される際に発生する排出量。
活動量の収集: 廃棄業者からの処理データを取得。
課題: 廃棄時のデータ不足が課題。
13. リース資産(下流)
概要: 他社にリース提供した資産の使用に伴う排出量。
活動量の収集: リース先からのエネルギーデータを収集。
課題: リース先企業とのデータ連携。
14. フランチャイズ
概要: フランチャイズ店舗の活動に伴う排出量。
活動量の収集: 加盟店からエネルギーデータを取得。
課題: 加盟店間のデータばらつき。
15. 投資
概要: 投資先の活動に関連する排出量。
活動量の収集: 投資報告書からの情報収集。
課題: 投資先企業からのデータ提供の不十分さ。
すべてのデータは、出典が明確であることが重要です。
特に、何の排出源からのデータかを認識し、その出典を認証できる資料を保存します。
また、これは公表情報の信頼性を保証するために必須です。
引用:https://www.env.go.jp/press/116491.pdf
5.Scope1,2,3指標の選定方法
排出原単位(Emission Intensity)は、企業活動におけるエネルギー効率や温室効果ガス(GHG)排出の効率性を示す重要な指標です。具体的には、以下のような算出方法が用いられます
算出方法
製品単位あたりの排出量
製品1単位を生産するために排出されるGHG量(例: kg CO₂/製品1単位)
売上高あたりの排出量
売上1円あたりのGHG排出量(例: kg CO₂/円)
エネルギー消費量あたりの排出量
使用エネルギー1MJあたりのGHG排出量
これらの指標は、企業が特定の活動領域における排出効率を把握し、改善を目指すための基盤となります。
指標選定時の考慮事項
業種別特性の反映
製造業、サービス業、農業などの業種によって適切な指標が異なるため、業界ベンチマークと比較する必要があります。
データの信頼性
データの収集元、計測方法、適用する排出係数の正確性を確認する必要があります。
国際基準との整合性
GHGプロトコルやISO14064に基づく指標を採用することで、国際的な競争力を確保します。
6.Scope1,2,3データ比較のための基準選定
企業間や地域間で排出量を比較する際には、統一された基準の適用が不可欠です。これにより、異なる条件下での排出量データが公平に評価されます。
比較のための要素
地域
電力供給源や気候条件に基づく排出係数が異なるため、地域ごとの特性を考慮します。
業界
製造プロセスやエネルギー消費構造が業界によって異なるため、業界ベンチマークを活用します。
企業規模
大規模企業と中小企業では排出効率やデータ収集能力が異なるため、同じ尺度で評価することは避けます。
基準化の方法
ISO14064: 温室効果ガス算定に関する国際基準。組織レベルおよびプロジェクトレベルでの排出量を正確に報告する方法を提供します。GHGプロトコル: Scope1、2、3に基づく排出量の分類と算定を標準化する枠組み。
7.Scope1,2,3における長期的な目標の設定
目標設定の枠組みでは下記のような時間軸で設定されます。
時間軸
1,短期目標(1~3年)
具体例: 節電対策の導入、エネルギー効率改善のための設備投資。
2,中期目標(3~10年)
具体例: 再生可能エネルギーの活用拡大、サプライチェーン全体での排出量削減。
3,長期目標(10年以上)
具体例: カーボンニュートラルの達成、次世代技術の導入。
目標達成に向けたプロセスとして、年度ごとに排出量データを収集し、進捗状況を評価します。
また実施した施策の効果を検証し、新たな課題に応じて戦略を修正します。
排出量削減の進捗管理
排出原単位を使用して年度ごとの削減進捗をモニタリングします
部門別の排出量比較
製造部門、物流部門、オフィス部門ごとに排出量を分析。
過去との比較
前年度比で排出量削減率を算出し、目標に対する進捗を評価。
Scopeごとのデータ比較
Scope1、Scope2、Scope3の排出量を比較し、削減効果の大きい領域を特定します。
Scope1: 直接排出を最優先で削減。
Scope2: 再生可能エネルギーの導入で効率化。
Scope3: サプライチェーンの効率化により大幅削減。
これらに対して具体的なKPIを設定し、削減戦略の効果を定量的に評価するケースもあります。
・売上高あたりの排出量削減率: 全社的な取り組みの進捗を測定。
・製品単位あたりのエネルギー使用量: 生産効率の改善効果を測定。
引用事例:https://www.j-front-retailing.com/sustainability/low-carbon/low-carbon06.html
引用事例:https://www.nesic.co.jp/sustainability/environment/teigen.html#anc-Col5