本記事では、GX推進法に基づき2024年発足したGX推進機構の設立背景・金融保証/賦課金スキームと、日本初の都市型キャップ&トレード「東京都排出量取引制度」の制度概要・2026年改定動向を整理し、サステナビリティ推進室が直面する資金調達、社内炭素価格設定、MRV強化、排出枠戦略を総合的に解説します。
GX推進機構(正式名称:脱炭素成長型経済構造移行推進機構)は、GX推進法(令和5年法第32号)に基づく「特別の法律に基づく認可法人」として2024年7月1日に業務を開始した。最大の使命は、今後10年間で150兆円超を見込むGX投資を加速させることであり、①金融支援、②成長志向型カーボンプライシング(賦課金+排出量取引)、③官民連携ハブという三本柱で事業を展開しています。
参考:https://www.gxa.go.jp/org/about/
※令和7年7月2日に経済産業省 GXグループにて発表された「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」を反映した内容は下記記事となります。



1. 設立の背景と法的枠組み
GX推進法と政策タイムライン
2022年末の「GX基本方針」──2050年カーボンニュートラルと経済成長の両立──を受け、政府は2023年にGX推進法を制定。続く2025年5月改正で排出量取引制度の義務化や化石燃料賦課金の導入時期(2028年度)など、具体スキームが法定化されました。
参考:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/ikousai/dai7/siryou1.pdf
ガバナンスと資本構成
資本金は2016.6億円。理事長に元健康保険組合連合会会長の筒井義信氏が就任し、財務・カーボンプライシング・金融審査など専門理事が分掌するマトリクス型組織を採用。民間金融やエネルギー企業出身者を登用し、ファイナンスと技術両面の審査力を備える体制です。
参考:https://www.gxa.go.jp/org/about/
2. 金融支援──債務保証・出資・社債引受け
債務保証3類型と保証割合
類型1:GX新技術導入案件──原則保証80%、GX特有リスク認定で最大95%
類型2:GX一般案件──原則50%、特定条件下で80%
類型3:トランジション・ファイナンス案件──原則50%、重要案件で90%
保証超過分(90〜95%)の履行は「事業者の責によらない事由」に限定される点が特徴で、金融機関に一定のリスクシェアを残す設計になっています。
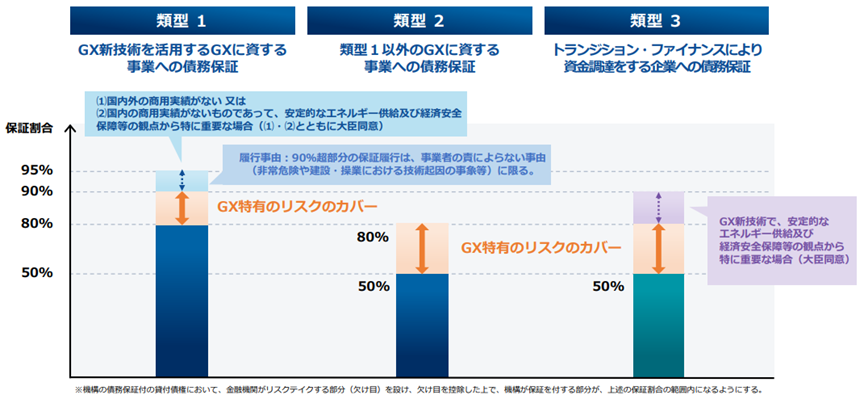
参考:https://www.gxa.go.jp/news/.assets/annualreport_FY2024.pdf
出資・メザニンファイナンス
出資先は①大型脱炭素プロジェクト、②GXファンド(LP出資)、③ディープテック・スタートアップの3類型。これにより商用化前後の死の谷を埋めるブレンデッド・ファイナンスを実装します。
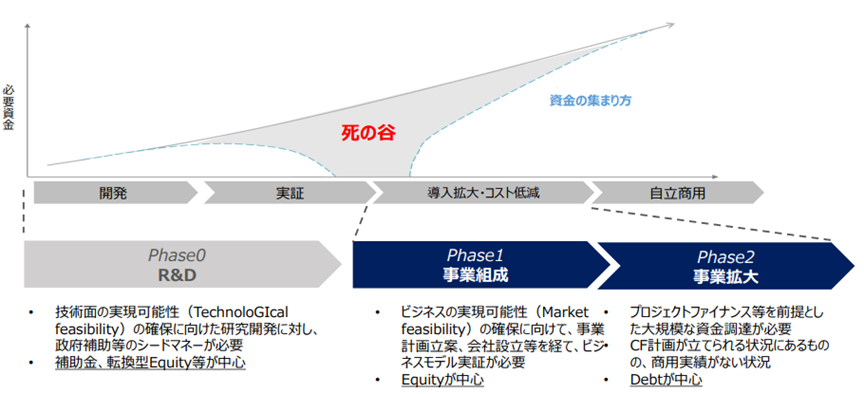
参考:https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2025/kokai/0606_2gaiyo.pdf
2024年度実績と相談件数
2024年度は開始半年で水素製造・送電網整備・CCUS関連等75件の相談が寄せられ、うち13件が保証審査入りしています(保証総額約1,250億円)。初弾案件は2025年夏の契約締結を目指しています。
3. 成長志向型カーボンプライシング──賦課金とGX-ETS運営
化石燃料賦課金の設計
2028年度導入に向け、化石燃料輸入量と発電用化石燃料消費量に対し課税。当面は1kg-CO₂あたり数円規模でスタートし、GX経済移行債の償還財源に充当する案が示されている
参考:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/ikousai/dai7/siryou1.pdf
排出量取引制度(GX-ETS)の市場運営
2026年度開始のGX-ETSでは、GX推進機構が排出枠取引市場を設置・運営し、現物取引の価格公示・清算・モニタリングを担う計画です。対象は直接排出10万t-CO₂以上の全業種、価格上限・下限を設定しつつ不履行ペナルティを1.1倍に抑制しています。
企業が準備すべき実務
- ・無償割当申請︓ベンチマーク・グランドファザリング方式の選択
- ・排出量算定報告︓第三者確認(登録確認機関)必須
- ・保有義務履行︓翌年度1月末に排出実績分の枠を保有
サステナビリティ推進室は、MRV体制の強化と社内炭素価格の導入で資本コスト上昇リスクを管理する必要がある。
4. GXハブ機能とナレッジ共有
技術審査・研究機関連携
2024年11月、産総研グループと連携協定を締結。技術レビュー委員会を共同設置し、案件審査で最新技術・LCA評価を反映する仕組みを整備しています。
案件組成支援と人材育成
機構内「GX Future Academy」が省庁・地銀・企業のGX担当者向けにケーススタディ型研修を提供。これまでに延べ1,200名が受講し、官民横断ネットワークを形成しています。
5. 企業インパクト——サステナビリティ推進室の視点
資金調達コスト
保証料率は保証割合と案件リスクに応じ0.2〜1.0%。民間金融単独よりもスプレッドが平均40bp低減すると試算され、CAPEX重いGX投資のNPV改善に寄与しています。
規制コストとインセンティブ
排出枠価格(上限8,000円/t-CO₂想定)と賦課金(初年度1,200円/t-CO₂想定)の二重コストを回避するために、効率的な削減・クレジット調達戦略が不可欠。逆に早期削減・イノベーション投資は機構保証による資金調達優遇やETS売却益を通じリターン源となります。
即時アクションリスト
・社内炭素価格の引上げ(5,000→10,000円水準)
・資金調達パイプラインの整理──機構保証対象技術の棚卸し
・排出データガバナンス強化──登録確認機関審査を見据えたERP改修
6. 今後の展望と課題
2025年改正法下での追加論点
・発電部門の排出枠オークション(2033年度〜)
・賦課金の段階的引上げと低所得者負担軽減措置
・ETS市場へのデリバティブ導入可否
財源・ガバナンス
GX経済移行債(CT国債)は2025年度1.5兆円を予定。市場からの「グリーンウォッシュ」批判に応えるため、第三者レビューとインパクト報告の質的向上が急務です。
国際連携と標準化
EU・韓国ETSとの相互リンク可能性、IFRS-ISSB基準との整合、CBAM対応など、国際標準化が企業競争力の鍵となります。
7. まとめ
GX推進機構は、 「リスクテイクを通じてGX投資のハードルを下げ、カーボンプライシングで行動変容を促す」 という二段ロケットで脱炭素と成長の同時実現を狙います。サステナビリティ推進室にとっては、①機構保証の積極活用、②ETS遵守とクレジットポートフォリオ構築、③データガバナンス高度化が喫緊の経営課題です。2025年改正法施行後の詳細規則策定フェーズで実務要件が固まるため、最新情報を継続的にウォッチし、社内の意思決定スピードを高めることが競争優位を左右するでしょう。













