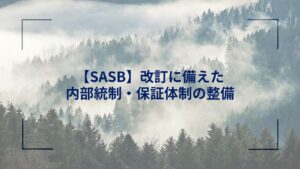1. グリーンボンド/ローンの概要と意義
グリーンボンドとは
グリーンボンドとは、資金使途を再生可能エネルギー、エネルギー効率化、クリーン交通、汚染防止、自然資源保護など環境改善に資するプロジェクトに限定して発行される債券です。2007年に欧州投資銀行(EIB)が世界初のグリーンボンドを発行して以降、市場は急速に拡大し、2022年時点で世界累計発行額が2兆ドルを超える規模に達しました。発行主体は政府・地方自治体、国際開発銀行、事業会社、不動産投資信託など多岐にわたり、調達資金で太陽光・風力発電の建設、鉄道など低炭素インフラの整備、グリーンビルディングの開発、水環境保全プロジェクトなどが世界中で進められています。日本でも2014年に日本政策投資銀行(DBJ)が国内初のグリーンボンド(グリーンビルディング向け)を発行して以来、自治体による環境債(例:東京都や長野県のグリーンボンド)や、電力・鉄道・不動産各社の発行が相次いでいます。
グリーンローンとは
グリーンローンは、銀行など金融機関が貸し手となり、借り手企業等が資金を環境プロジェクトに限定して使用することを契約上定めた融資形態です。近年はプロジェクトファイナンスや事業会社向けのコーポレートローンにもグリーンローンの手法が取り入れられ、再エネ発電所建設資金やグリーンビル取得資金を調達するケースが増加しています。債券と異なり非公開で双務契約の融資ですが、金融機関側のサステナビリティ方針に沿って貸出条件(金利優遇など)が設定されることもあり、企業にとっては柔軟な資金調達手段となっています。
グリーンファイナンスの意義
グリーンボンド/ローンの意義は、環境分野への資金の流れを可視化・促進する点にあります。調達資金が明確にグリーンプロジェクトに充当されるため、投資家・貸し手はその資金がもたらす環境改善効果(CO2削減量、汚染物質削減量等)の報告を受け取ることができます。これにより、環境に配慮したプロジェクトへの資金供給が拡大し、発行体・借り手にとっても環境経営のPR効果や社内のESG意識向上につながるという側面があります。
2. 国際的な基準とガイドライン
グリーンボンド原則(GBP)
グリーンボンド市場の信頼性を維持するため、ICMAが2014年に制定したグリーンボンド原則 (Green Bond Principles, GBP) が国際的なベースラインとなっています。GBPは発行体が満たすべき4つのコア要素を定めています:
- 資金使途 (Use of Proceeds): 調達資金は明確に環境改善目的のグリーンプロジェクトに充当すること。原則は具体的な「グリーン」の定義付けは行わず、再エネ、エネルギー効率、クリーン交通、水資源・廃棄物管理、生物多様性保全等のプロジェクトカテゴリを例示しています。
- プロジェクト評価と選定のプロセス: 発行体はどのように適格グリーンプロジェクトを特定・評価するか、その基準や持続可能性目標との整合性を開示すること。
- 資金管理: 調達した資金が適格プロジェクトに確実に充当されるよう、社内で分別管理し、残高や割当状況を把握・記録すること。
- レポーティング: 少なくとも年1回、資金の充当状況およびプロジェクトの環境インパクト(定量的効果指標など)を開示すること。
グリーンボンド原則は自主的ガイドラインですが、現在ほとんどのグリーンボンド発行体がこれに従っており、市場のデファクト標準となっています。また、多くの場合、発行時に第三者機関(環境専門評価機関)からのセカンドパーティ・オピニオンを取得し、資金使途やプロジェクトの環境貢献度が原則に沿って適切であるとのお墨付きを得るのが一般的です。評価機関の例として、ノルウェーのCICEROや米国のSustainalytics、日本の日本格付研究所(JCR)などがグリーンボンドの外部評価サービスを提供しています。
グリーンローン原則(GLP)
ローン分野では、ローンマーケット協会(LMA)等が2018年にグリーンローン原則 (Green Loan Principles, GLP)を公表し、基本的内容はグリーンボンド原則の4要素をそのまま適用する形となっています。すなわち、「資金使途」「プロジェクト評価・選定」「資金管理」「報告」の各項目について、貸し手・借り手が遵守すべき事項を示したものです。GLPの策定により、融資においても債券と同等の透明性・説明責任が求められるようになり、市場の健全な発展が促されています。日本でも環境省が2017年に「グリーンボンドガイドライン」を策定し、2020年および2022年に改訂を行うなど、国内実情に合わせたガイドライン整備が行われています。これらはGBP/GLPと整合しており、発行体・借り手が遵守すべき事項を日本語で詳細に説明したものです。
各国のローカルガイドライン
ローン分野では、ローンマーケット協会(LMA)等が2018年にグリーンローン原則 (Green Loan Principles, GLP)を公表し、基本的内容はグリーンボンド原則の4要素をそのまま適用する形となっています。すなわち、「資金使途」「プロジェクト評価・選定」「資金管理」「報告」の各項目について、貸し手・借り手が遵守すべき事項を示したものです。GLPの策定により、融資においても債券と同等の透明性・説明責任が求められるようになり、市場の健全な発展が促されています。日本でも環境省が2017年に「グリーンボンドガイドライン」を策定し、2020年および2022年に改訂を行うなど、国内実情に合わせたガイドライン整備が行われています。これらはGBP/GLPと整合しており、発行体・借り手が遵守すべき事項を日本語で詳細に説明したものです。
EUタクソノミーと規制動向
さらに、EUは「EUタクソノミー」(持続可能な経済活動の分類基準)を2020年より施行し、どのような活動が「環境的に持続可能」と見なせるか技術的基準を定めました。例えば発電であればCO2排出強度の閾値が規定され、これを下回る発電所建設がグリーン適格となる、といった具合です。タクソノミーは域内の公共・民間の投資判断指針として機能しており、EUは将来的にEUグリーンボンド規則を導入して、タクソノミーに適合する資金使途のみをグリーンボンドと称する公式認証制度を運用する見込みです。こうした規制面の動きは、グリーンボンド市場の信頼性向上と定義の明確化に寄与すると期待されます。
3. 活用事例と市場動向
代表的活用事例
グリーンボンド/ローンは多種多様な主体に活用されています。その典型例として再生可能エネルギー発電事業があります。世界銀行やアジア開発銀行、民間電力会社などが再エネ発電プロジェクト向けにグリーンボンドを発行し、太陽光・風力発電所の建設資金としてきました。またクリーン交通インフラへの資金供給も盛んです。例えばフランス国鉄は高速鉄道網拡充のためのグリーンボンドを発行し、JR東日本も新型エネルギー効率車両導入資金にグリーンボンドを活用しました。空港分野では羽田空港が環境負荷軽減策(LED照明や太陽光設備導入)資金としてグリーンボンドを活用した例があります。地方自治体も、東京都が気候変動対策事業に充当するグリーンボンドを発行したほか、長野県など複数の自治体が気候非常事態宣言に基づく環境投資債を発行しています。
市場規模と発行動向
市場全体の動向を見ると、グリーンボンド発行額は年々増加し、2021年には新規発行が年間5,000億ドルを超え過去最高を記録しました。しかし2022年は世界的な金利上昇や市場混乱の影響でやや減速したものの、それでも年間3,320億ドルの発行があり累計2兆ドルに達しています。2023年以降は再び増加基調に戻り、各国のグリーン復興計画やエネルギー危機への対応投資を背景に市場はさらなる成長が見込まれます。一方、日本国内の発行額は年間数千億円規模で横ばい傾向でしたが、政府のグリーンボンド発行(2022年に初のソブリーングリーンボンド発行)や、脱炭素関連の大型投資計画に伴う民間発行の増加が期待されています。
日本市場の状況
市場全体の動向を見ると、グリーンボンド発行額は年々増加し、2021年には新規発行が年間5,000億ドルを超え過去最高を記録しました。しかし2022年は世界的な金利上昇や市場混乱の影響でやや減速したものの、それでも年間3,320億ドルの発行があり累計2兆ドルに達しています。2023年以降は再び増加基調に戻り、各国のグリーン復興計画やエネルギー危機への対応投資を背景に市場はさらなる成長が見込まれます。一方、日本国内の発行額は年間数千億円規模で横ばい傾向でしたが、政府のグリーンボンド発行(2022年に初のソブリーングリーンボンド発行)や、脱炭素関連の大型投資計画に伴う民間発行の増加が期待されています。
4. グリーンファイナンスの課題と展望
グリーンウォッシング防止
グリーンボンド/ローンは成熟しつつある市場ですが、依然として課題も存在します。最大の課題は、やはりグリーンウォッシング防止です。発行体が「グリーン」と称しながら実態は疑わしいプロジェクトに資金を投じるリスクを抑えるため、外部レビューの質や、タクソノミー等による統一的な適格性基準の整備が不可欠です。EUタクソノミーはその一環として高水準の基準を設けましたが、厳しすぎる基準は資金調達のハードルを上げるとの指摘もあり、実効性と実用性のバランスが問われます。また発行体側にとっては、使途を縛るグリーンボンドよりも自由度の高いサステナビリティ・リンク債等へシフトする動きも見られ、市場間の競合も意識されています。
市場間の競合とテーマ債
グリーンボンド/ローンは成熟しつつある市場ですが、依然として課題も存在します。最大の課題は、やはりグリーンウォッシング防止です。発行体が「グリーン」と称しながら実態は疑わしいプロジェクトに資金を投じるリスクを抑えるため、外部レビューの質や、タクソノミー等による統一的な適格性基準の整備が不可欠です。EUタクソノミーはその一環として高水準の基準を設けましたが、厳しすぎる基準は資金調達のハードルを上げるとの指摘もあり、実効性と実用性のバランスが問われます。また発行体側にとっては、使途を縛るグリーンボンドよりも自由度の高いサステナビリティ・リンク債等へシフトする動きも見られ、市場間の競合も意識されています。
今後の成長ドライバー
今後の展望として、各国政府や国際機関の支援策(利子補給や保証など)が拡充されれば、発行コスト低減につながり更なる市場拡大が期待できます。投資家側でもESG投資の主流化に伴い、債券ポートフォリオの一定割合をグリーンボンドに充当する動きが一般化しつつあります。こうした資金の受け皿として、グリーンボンド市場は引き続き高成長が見込まれ、世界のサステナブル投資推進の原動力であり続けるでしょう。
5. まとめ
それでも、グリーンボンド市場の果たす役割は大きく、投資家層の拡大や商品イノベーションも進んでいます。例えば最近では「ブルーボンド」(海洋保全目的)や「トランジションボンド」(前述)など派生的なテーマ債も生まれています。また、発行体が環境のみならず社会的課題にも取り組む場合には「サステナビリティボンド」(調達資金をグリーン及びソーシャル両方のプロジェクトに充当)が活用されるケースもあります。日本でも脱炭素だけでなく防災・適応策や地域創生と組み合わせた資金調達が模索されており、グリーンファイナンスの裾野は広がっています。