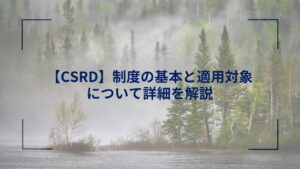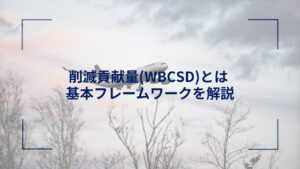EUが制定した企業サステナビリティ報告指令(CSRD)は、従業員500人超の上場企業など大企業に対し、2024年度(2025年報告)から環境・社会・ガバナンス(ESG)情報の包括的な開示を義務付けるものです。各国の国内法整備が進行中ですが、2025年4月時点ではドイツやスペインなど国内法制化が完了していない国の企業からも、自発的にCSRDに基づく開示を行う動きが見られます。実際、時価総額が数兆円規模に及ぶ欧州のグローバル企業は、2024年12月期の年度報告において、CSRDおよび対応する欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に沿ったサステナビリティ情報の開示を始めています。これらの企業では、財務情報と一体となったサステナビリティ報告(ダブルマテリアリティ原則に基づく開示)を行い、ビッグ4監査法人等による限定的保証(将来的な合理的保証への移行を視野)も付与され、情報の信頼性を高めています。


1. 主要企業のCSRD開示事例
以下では、BMW(BMW AG)、アディダス(adidas AG)、シェル(Shell plc)、ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)、ユニリーバ(Unilever plc)、シーメンス(Siemens AG)といったグローバル大手企業におけるCSRD開示の状況と特徴を分析します。
BMW(BMW AG)
自動車業界のBMWは、2024年の年次報告書「BMWグループ報告書 2024」において、財務報告とサステナビリティ報告を統合した形でCSRDに準拠した開示を行いました。サステナビリティ情報は経営報告書の一部として記載され、財務諸表とともに監査人であるPwCによる監査・保証を受けています。これにより、環境・社会情報も財務情報と同等の信頼性が担保されています。内容面では、気候変動対策や多様性推進など長期目標を明確に示している点が特徴です。例えば2030年までに新車販売の50%超を電気自動車とすること、自社のスコープ1・2排出量を2019年比で50万トン以上削減、製品使用段階を含むバリューチェーン全体のスコープ3排出量を4,000万トン以上削減する目標、さらに管理職に占める女性比率を23〜25%に引き上げる目標など、定量的なKPIを掲げています。これらの目標と進捗が統合報告書で詳述されており、経済価値の創出と環境・社会責任の両立に向けた360度の取り組みを示すホリスティックな開示となっています。
https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/ir/downloads/en/2025/bericht/BMW-Group-Report-2024-en.pdf
アディダス(adidas AG)
消費財業界のアディダスは、サステナビリティ報告の長い歴史を持ち、2024年報告では初めてCSRDおよびESRSの要求事項に完全準拠した開示を自主的に実施しました。アディダスはダブル・マテリアリティ評価(Double Materiality Assessment)を行い、自社の事業に関連するあらゆる重要な影響・リスク・機会を洗い出しています。その結果、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の各トピックについてESRSが定める全ての重要サステナビリティ事項を網羅的に報告するに至りました。具体的には、気候変動への対応(例:2050年までのネットゼロ達成目標と2030年までの中間目標)、資源循環と製品の持続可能性(例:リサイクル素材の活用拡大やプラスチック廃棄物削減)、サプライチェーンの労働環境・人権(例:調達先工場の監査と改善)など、アディダスの事業活動に関わる広範なESG課題について詳細な情報開示を行っています。これらの情報には財務監査と同じPwCによる保証が付与されており、ステークホルダーに対する透明性と説明責任を強化しています。長年培ってきたサステナビリティへのコミットメントをベースに、新基準に沿った包括報告にいち早く移行した好例と言えます。
https://www.adidas-group.com/en/sustainability/resource-center/sustainability-reporting
シェル(Shell plc)
エネルギー業界のシェルは、2024年の年次報告書(2025年3月公表)において初のCSRD準拠「サステナビリティ情報開示(Sustainability Statements)」セクションを導入しました。これまで27年間にわたり発行してきた独立のサステナビリティ報告書を廃止し、財務情報とサステナビリティ情報を一冊の年次報告書に統合する大胆な方針転換を行っています。この統合報告では、気候変動対策(移行戦略や2050年ネットゼロ目標、CO₂排出実績)、生物多様性保全(事業による生態系影響の評価と対策)、汚染防止と資源循環(大気・水質汚染防止措置や廃棄物管理)、水資源管理、従業員の多様性・労働安全、バリューチェーン上の労働者(請負先やサプライヤーの労働基準)、地域社会への影響と関与、企業倫理・ビジネス行動(贈収賄防止やロビー活動の開示)など、CSRDが要求する広範なトピックを網羅的に取り扱っています。各テーマについて定量データと定性的説明が盛り込まれ、シェルの持続可能性への取り組みを全方位で評価できる内容となっています。これらのサステナビリティ情報には財務監査人と同じEYによる限定的保証が付与され、信頼性も確保されています。シェルの事例は、財務と非財務の完全統合報告によって企業戦略とサステナビリティを不可分に示す先進的取り組みとして注目されます。
https://www.shell.com/sustainability/reporting-centre.html
ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)
金融業界のドイツ銀行は、2024年の年次報告に**「サステナビリティ・ステートメント」**と題する章を設け、CSRDに準拠したESG情報の開示を行いました。ドイツでは現行の商法(HGB)で非財務報告が義務化されていますが、同行は欧州基準であるESRSを適用する形で報告内容を構成しています。まず、ダブルマテリアリティ分析により、自社にとって重要なサステナビリティ課題を特定しました。気候変動や持続可能な金融(融資ポートフォリオの気候リスク、グリーンファイナンス目標)、多様性と人材(ジェンダー多様性目標、人材育成)、コンプライアンスとガバナンス(リスク管理体制の強化等)といったトピックが重要事項として抽出され、それらに沿って開示が行われています。特徴的なのは、報告内容の絞り込みと二層化です。ESRSに基づく重要事項以外のテーマ(例えば社内の施設における環境負荷や社会貢献プログラムなど)は、主要なサステナビリティ・ステートメントでは簡潔に触れるか割愛し、代わりに補足資料として「サステナビリティ・データ補遺」を別途公開しています。補遺には追加の指標や過年度データが含まれますが、それらは必ずしも監査保証の対象とはせず、主要レポート部分とのメリハリを付けている点が興味深いです。主要なESG指標については監査人であるEYによる限定的保証を受けており、重要事項に絞った情報に対して信頼性を確保しつつ、補足情報も開示することでステークホルダーの多様な関心に応えようとする姿勢がうかがえます。
https://investor-relations.db.com/files/documents/other-presentations-and-events/2024/Annual-Report-2024.pdf
ユニリーバ(Unilever plc)
生活消費財のグローバル企業であるユニリーバは、英国籍企業ながらEUのCSRD趣旨に賛同し、2024年の年次報告書(2025年3月発行)でCSRDに準拠したサステナビリティ開示を行いました。同社は長年「サステナブル・リビング・プラン」など先進的なESG戦略を展開してきており、その延長線上でCSRD対応を早期に取り入れた形です。ユニリーバの開示では、まずダブルマテリアリティ評価によって自社の人々・地球に対する影響(インパクト)と、事業へのリスク・機会の双方を分析し、各サステナビリティ課題を「ポジティブ」「ネガティブ」「中立」と評価している点が特徴です。例えば、自社の政策提言やロビー活動について、CSRDの求めに応じて影響を評価し、「気候変動対策に資するポジティブな影響を与えている」と自己評価を行いました。このように企業の社会的影響を定性的に表現する開示は議論も呼びましたが、CSRDによる透明性向上の一例といえます。報告内容自体は、環境面では2039年までのバリューチェーン全体でのネットゼロ目標に向けた進捗、プラスチックや水資源の削減、森林破壊ゼロのサプライチェーン構築など、社会面では多様性・包摂の目標(管理職に占める女性比率向上等)やコミュニティ投資、ガバナンス面では倫理規程の徹底や取締役会のサステナビリティ監督体制など、多岐にわたる項目を網羅しています。これらのデータと記述には監査人であるKPMGによる保証が付与されました。ユニリーバの事例は、自社の長期ビジョンに沿って積極的にCSRD基準を取り込み、定性的評価も含めた高度な情報開示を行ったものとして評価できます。
https://www.unilever.com/files/unilever-annual-report-and-accounts-2024.pdf
シーメンス(Siemens AG)
産業機械・インフラ領域のシーメンスは、CSRD対応を見据えた報告基盤の整備を進めています。ドイツ本国でのCSRD法制化スケジュールに合わせ、正式なCSRD準拠開示は2025年度報告からと見られますが、2024年度において既にダブルマテリアリティに基づく包括的なマテリアリティ評価を実施しました。その結果、15の重要サステナビリティ課題を特定し、特に「気候変動対策」と「持続可能な製品設計・ライフサイクルマネジメント」が最も重要な課題として挙げられています。シーメンスは独自のサステナビリティ戦略フレームワークである「DEGREE」(Decarbonization:脱炭素、Ethics:倫理、Governance:ガバナンス、Resource Efficiency:資源効率、Equity:公正、Employability:働きがい)を掲げており、今回特定された重要課題もDEGREEの各要素と対応付けられています。例えば、環境面では自社運営でのCO₂排出を2019年比55%削減するとともに、製品・ソリューションを通じて顧客の排出削減に貢献(2024年度の販売製品によりライフサイクル全体で1億トン超の排出削減効果を創出)していることを開示しています。また、ガバナンス面では取締役会レベルでサステナビリティ委員会を設置し、役員報酬にESG目標を連動させる仕組みを導入済みです。こうした体制・戦略の下、GRI基準による従来の「影響重視」のマテリアリティ評価とCSRDの二重の観点を組み合わせ、両者を補完的に活用することで情報開示の信頼性と網羅性を高めています。シーメンスはCSRDに正式対応する前段階から周到な準備を行っており、既存のサステナビリティ報告を進化させつつ新たな規制要件に適合させる優良例と言えるでしょう。
https://www.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/webinars/23-en/2307-sustainability-csrd.html
2. まとめ
以上、欧州を代表する大企業におけるCSRDに基づく開示事例を概観しました。各社とも業種に応じた重点領域を持ちながらも、共通してダブルマテリアリティに根ざした網羅的なESG情報開示へと踏み出している点が特徴です。これは単に規制への対応というだけでなく、ステークホルダーとの対話や企業価値向上の観点からも重要な意味を持ちます。加えて、多くの企業が財務報告と非財務報告の統合を進め、監査法人による保証を付すことで、サステナビリティ情報の信頼性と比較可能性を高めています。CSRD開示の先行事例からは、戦略と一体化したサステナビリティ経営の姿勢と、透明性・説明責任への強いコミットメントが読み取れます。今後も欧州発のこの潮流が世界の企業報告に与える影響は大きく、ビジネスの持続可能性を情報開示の面から支える動きが一層広がっていくと考えられます。
引用
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20250421.html