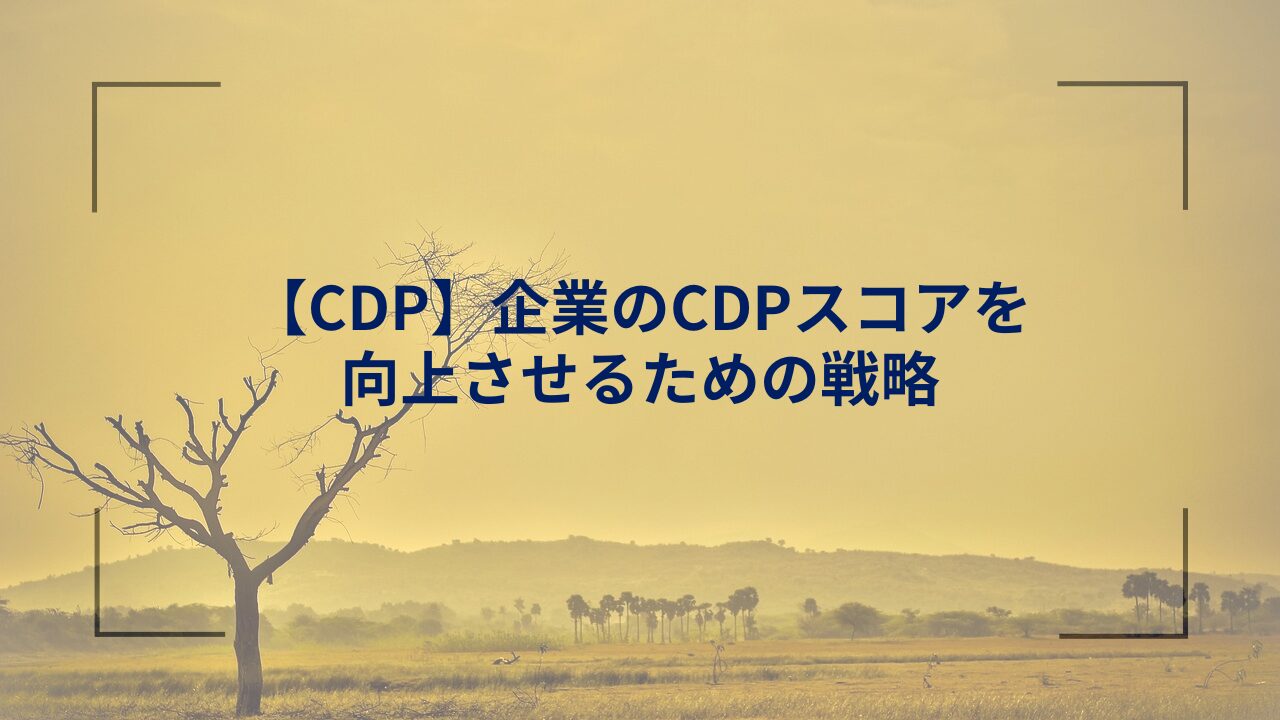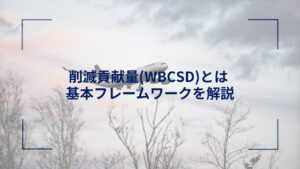CDPスコアを高めるには、排出量や水使用の定量的開示、科学的な目標設定、経営陣の関与、リスク分析、具体的施策の実行と効果報告が不可欠です。特にA評価を目指すには、戦略的かつ透明な対応が求められます。本記事では、CDPスコアリングの仕組みと企業が実践すべき重点戦略、さらに先進企業の成功事例を通じて、高スコアを獲得するための道筋を解説します。


1. CDPスコアリングの仕組み
前述の各記事で詳述したように、CDPは気候変動・水セキュリティ・森林の各プログラムで企業回答を評価し、AからD-までのスコアを付与しています。ここでは改めてCDP全般のスコアリング枠組みを整理し、高スコア獲得のための戦略の土台とします。CDPの評価は、大きく4つのレベルに分類されます。
リーダーシップ・レベル(A、A-)
業界トップクラスの包括的かつ先進的な取り組みを行っている企業。環境課題の認識が深く、具体的な目標と実績、戦略的行動、透明性の高い開示によって他の模範となる。
マネジメント・レベル(B、B-)
環境リスクと影響を十分に把握し、対策を講じている企業。目標やポリシーが整備され、一定の実行が伴っている。
認識・リスク定義レベル(C、C-)
自社の環境上の課題やリスクを認識している段階の企業。取り組みは始まっているが、体系的な対策や目標はこれからという状況。
情報開示レベル(D、D-)
とりあえず情報開示は行っているが、対応が限定的または初期段階にとどまる企業。データ開示が中心で、目立った対策はまだ実施できていない状況。この他に未回答(F)があります。期限内に回答しなかった企業は自動的にFとなり、スコア表に「-」で示されます。
2. 評価項目
CDPのスコアリング基準は、上記レベルを決定するために各質問ごとに細かな配点と評価項目が設定されています。たとえば気候変動プログラムでは、「排出量データを開示したか」「削減目標を持っているか」「その目標が科学的か」「取締役会が監督しているか」等、多数の質問に点数が割り振られています。その合計点に応じてD~Aが決まるイメージです。ただし単純な点数だけでなく、各レベルへの到達基準が設けられており、一定の要件を満たさないとB以上にはなれない等の仕組みがあります。評価基準を一言で言えば、「詳細かつ包括的な情報を開示し、環境課題への認識・対応・成果が明確に示されているか」です。具体的には以下です。
情報開示の度合い
質問に対して具体的なデータや内容を開示しているか(単にYes/Noではなく自由記述含め)。
認識の深さ
自社のリスク・機会・影響を適切に認識・評価しているか。
管理と統合
組織として目標・方針・プロセスを整備し、経営に統合しているか(ガバナンスやリスク管理)。
実践と進捗
実際に行動を起こし、定量的な進捗や成果が出ているか。
リーダーシップ要素
他社を先導するような高い目標、イニシアチブへの参加、バリューチェーン全体への働きかけなどがあるか。
スコアAを取得する企業は、これら全ての面で非常に優れていることを示さなければなりません。CDP自体も「Aリスト企業は最も正確な情報を持ち、最も適切な行動を取れる企業」と表現しています。逆に言えば、高スコア企業に共通する要素を押さえることで、自社のスコア向上の指針が見えてきます。以下、その要素を踏まえた具体的戦略を述べます。
3. 企業が取り組むべき重点領域
CDPスコアを上げるために企業が注力すべき領域は、前節の評価基準と対応しています。特に重要度の高いものを順に挙げます。
データの網羅的開示と精度向上
最低限、CDP質問書で求められる定量データは全て提供しましょう。GHG排出量(Scope1,2,3)、エネルギー消費、水使用量、森林リスク原材料の使用量等、自社で把握できていないデータがある場合は早急に測定・算定の仕組みを整備します。データに抜けや曖昧さがあると、Disclosureレベルどまりになってしまいます。また、第三者検証(Assurance)を受けたデータであれば信頼性が高く、評価も向上します。例えばGHG排出量はISO14064-3等の検証報告書を取得し、そのことをCDP回答で示すと良いでしょう。
明確な目標と実績管理
気候変動であれば科学的削減目標(SBT)、水であれば削減・再利用目標、森林であれば認証調達率目標など、各領域で短期・中長期の数値目標を設定します。そして、その進捗状況(毎年の実績値)をトラッキングして報告します。目標は野心的であるほどLeadershipに近づきますが、未達で大きく後れを取ると評価に響くため、現実的かつ高い目標をバランスよく設定することが大切です。目標未達の場合も、理由分析と今後の改善策を回答することで誠実さを示すことが必要です。
ガバナンス体制の構築
取締役会レベルの関与(Board Oversight)は高スコアの必須条件です。したがって、環境・サステナビリティ課題を経営議題として定期的に扱う仕組みを用意します。例えば「年2回のサステナビリティ委員会を取締役会内に設置し、CEOが議長を務めている」「環境KPI(例えばGHG排出原単位)が経営陣の業績評価に組み込まれている」等、トップマネジメントのコミットメントを具体的に示します。既にそのような体制がある場合は、CDP回答で詳細に記述し、関連する資料(CSR報告書の記載など)を参照させると評価者の理解を得やすくなります。
リスク・機会の詳細な分析
気候変動や水・森林に関するリスク評価を定量定性の両面から行い、その結果を回答で丁寧に説明します。シナリオ分析の活用はAレベルの企業ではほぼ必須と言えます。たとえば2℃シナリオにおける自社事業への影響額試算や、特定の水ストレス地域からの収益割合算出など、踏み込んだ分析を実施しましょう。そこまでできなくても、少なくとも全主要事業におけるリスク項目を洗い出し、発生確率・影響度・対応状況を一覧化して示すべきです。機会についても忘れずに評価します(新製品需要、コスト節減機会など)。これら分析プロセスや重要リスクの特定状況は、自由記述で詳細に記載することで高ポイントを得やすくなります。
具体的な対策と行動の証拠
単に計画や方針があるだけでなく、実際に実行した施策とその成果を示すことが決定的に重要です。例えば「前年に省エネ投資を○件行い、年間△トンのCO₂削減を達成」「工場Xで水リサイクルシステム導入し、取水量を〇%削減」など、成果に結びついた具体策を数多く報告します。また、自社内だけでなくサプライチェーンや製品ユーザーに広がる取り組み(Scope3対策やお客様向けの環境貢献製品など)も記載し、取り組みの幅広さをアピールします。できれば事例として、先進的な施策を深掘りして紹介すると説得力が増します(STAR法が有効です)。
ステークホルダーとのエンゲージメント
高スコア企業は、社外のステークホルダーとも連携しつつ変革を進めています。従って、投資家・顧客・サプライヤー・従業員・地域社会などとの対話や協働の状況を積極的に報告します。例: 「主要サプライヤー50社にCDP回答を依頼し、80%が回答」「地域行政と共同で洪水対策プロジェクトに参画」「国際イニシアチブ(例: RE100, SBTi Business Ambition)にコミット」などです。これらはLeadershipレベルの要素で、差別化になります。
継続的改善
回答内容から、企業が継続的に改善を図っている姿勢を読み取れることも重要です。例えば「昨年のCDPフィードバックを受け、未整備だったデータ管理プロセスを改善した」「新たな長期戦略『○○2050』を策定し、TCFD報告も拡充した」等、年々前進している様子を盛り込むと評価者に好印象を与えます。CDPスコアは一度に跳ね上がることは少なく、段階的な努力の積み重ねで向上します。そのプロセス自体を説明することは有益です。
以上の重点領域に体系的に取り組むことで、企業はCDPスコアを着実に向上させることができます。特に、今現在CやBに留まっている企業がAを目指すなら、トップマネジメントの関与強化と数値目標+実績のセット提示、そして第三者が見ても明確なエビデンス(データ・事例)の提示が欠かせません。
4. CDPの高スコアを獲得する企業事例
最後に、実際にCDPで高スコアを獲得している企業の成功要因を振り返ります。これは前述の重点領域が実践されている例でもあります。
花王(4年連続トリプルA)
花王は気候変動・水・森林すべてでA評価という偉業を成し遂げています。その要因は、徹底したデータ管理と目標志向、組織横断の取り組みにあります。GHG排出量削減ではSBT1.5℃認定目標を設定し、2040年カーボンゼロ・2050年カーボンネガティブという明確なビジョンを示しました。その実現に向け、工場単位の排出削減施策(バイオマスボイラー導入など)を進め、各施策の効果を定量化して報告しています。また経営層の関与も強く、環境経営委員会を設置し取締役会レベルでモニタリングしています。水では2030年に向けた節水目標を掲げ、製品開発で水使用削減のイノベーション(洗剤のすすぎ1回化など)を達成しました。森林ではRSPOやFSC等認証を推進し、パーム油のトレーサビリティをダッシュボードで公開、インドネシア農園支援で社会貢献も果たしています。さらに、花王はTCFD提言に沿った詳細な開示や、自社の取組みを積極的に社外発信する広報も展開し、透明性とコミットメントの強さで高評価を得ています。「全社的かつ科学的アプローチ」と「定量目標に基づく着実な実行」がトリプルAの秘訣と言えるでしょう。
https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20240206-001
資生堂(気候変動・森林ダブルA)
資生堂は2023年度に気候変動と森林の2分野でAリスト入りしました。同社は2030年までにスコープ1・2排出を60%削減(2019年比)というSBT目標を掲げ、2050年ネットゼロを宣言しています。再生可能エネルギー100%化(RE100)にもコミットし、2022年時点で国内外自社サイトでの再エネ電力比率を大幅に高めました。森林分野では、紙包装やパーム油の100%持続可能調達目標を定め、2023年時点でパーム油についてRSPO Book&Claimで100%達成しています。また、これらの方針・進捗を積極的に開示し、TCFD・TNFDレポートを発行してステークホルダーに説明責任を果たしています。資生堂の成功要因は、「国際基準に沿った高水準の目標設定」と「それを裏付ける施策(再エネ化や持続可能原料転換)の実行」にあります。さらに、ダブルAは単独ではなく組織横断のチームワークの成果であり、環境・CSR部門と事業部門が連携してイノベーション(例:サステナブルな原材料開発)に取り組んだ点も大きいでしょう。
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003774
積水ハウス(トリプルA)
積水ハウスは2023年にトリプルA(全分野A)を獲得しました。同社は早期から環境経営を掲げ、2050年までの長期ビジョン「積水ハウス 2050年のわが家」を策定して脱炭素・生物多様性・循環型社会の3テーマに注力しました。気候変動では、住宅の93%をZEH化(ネットゼロエネ住宅)するなど事業戦略と環境目標を融合させた点が秀逸です。その結果、Scope3(住宅使用時)排出大幅削減を実現し、社外にもインパクトを与えました。森林では独自の木材調達基準と「5本の木」計画で生態系配慮を進め、TNFDフレームワーク先行導入など先端的な開示を行っています。水については業種的に使用量は多くないものの、工場での循環水利用等を行い、姿勢を示しました。積水ハウスのトリプルAは、本業そのものを通じて環境価値を創造している点が大きな特徴です。環境課題を制約でなくイノベーションの機会と捉え、自社の商品力強化と社会貢献を両立させたことが最高評価につながりました。
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2024/20240206
以上の事例に共通するキーワードは、「経営戦略への統合」「定量目標管理」「革新的施策」「高い透明性」です。高スコア企業は、環境対応を全社戦略に組み込み、部門横断で取り組み、数値で成果を証明し、外部にオープンな情報開示をしています。自社がすぐにトリプルA企業と同じことを全てできなくても、まずはできる範囲で最善を尽くし、その結果を詳細に報告することが重要です。
CDPは努力の方向性を示してくれる羅針盤ですから、そのガイダンスに沿って改善を重ねれば、必ずスコアは向上します。例えば、初回回答ではDやCでも、翌年にデータ精度を上げてB-になり、さらに目標設定や社内体制整備を進めてB+へ、とステップアップするケースは多々あります。CDPからは個別フィードバックレポート(各質問の得点とピア企業比較)が提供されるので、それを活用して弱点を補強することも重要です。たとえば「リスク評価の項目で満点を取れていない」ならシナリオ分析導入を検討する、「目標の項目が弱い」ならSBT設定を目指す、という具合です。
5. CDPまとめ
最後に、CDPスコア向上の取り組み自体が社内の意識改革と能力向上につながることを強調したいと思います。CDPに真剣に向き合う企業は、自然と環境データ管理やサステナ戦略策定の社内スキルが高まり、部門間連携も進みます。それは将来的に必ず企業の強みとなります。したがって、CDPスコアを上げること自体を目的にするのではなく、環境経営のレベルを上げる過程の副産物としてスコアが上がるという発想が望ましいでしょう。CDPで高評価を得る企業は、その姿勢と能力において確かに卓越しています。しかし、それらは特別な企業だけの専売特許ではなく、他の企業も学び実践できるものです。本記事で紹介した戦略と事例を参考に、自社のCDP対応計画をブラッシュアップしていただければ幸いです。
引用
CDP 気候変動質問書スコアリング基準 2023年版
https://www.koei-j.co.jp/cdp-2022/