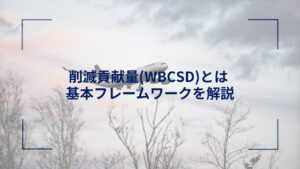CDPは、企業の気候変動対応を評価する国際的な情報開示枠組みで、温室効果ガス排出量の測定・開示、削減目標の設定、戦略・リスク管理、ガバナンス体制まで幅広く問います。日本企業でも対応が急速に進んでおり、投資家や市場からの信頼を得る上でも重要性が高まっています。本記事では、CDPと気候変動における企業の具体的な対策と報告義務について解説します。


1. CDP気候変動プログラムの概要
CDPの気候変動プログラムは、企業の気候関連情報を包括的に収集・評価する国際的な情報開示枠組みです。具体的には、企業の温室効果ガス排出に関するデータや気候変動対策の内容を質問書形式で毎年ヒアリングし、その回答に基づいて評価スコアを付与します。質問書の内容はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言と整合して設計されており、ガバナンス(経営層の関与)、戦略(事業戦略への気候課題の統合)、リスク管理(気候関連リスク・機会の特定と対応)、指標と目標(排出量などの指標と削減目標)という4つの柱に沿って情報開示が求められます。
設問項目
例えば、取締役会での気候変動問題の監督体制、移行リスク・物理的リスクの評価と事業影響、GHG排出量(スコープ1・2・3)の測定結果、それらを削減するための方策と目標などが主要な設問項目です。気候変動質問書は非常に幅広い項目を含みます。CO₂など温室効果ガスの排出量に関する定量データ(各スコープ別の排出量や前年度比の増減)、気候変動が事業に与えるリスクと機会の質的評価(規制動向や市場変化、極端気象の影響など)、内部カーボンプライシングの有無と活用方法、気候関連目標(削減目標値や再生可能エネルギー導入目標)の設定状況、気候変動に関する社内の統治(担当役員や報告ライン)など、多岐にわたります。これらの情報を通じて、CDPは企業が気候変動にどれだけ主体的かつ体系的に取り組んでいるかを評価します。
評価項目
「気候変動」分野で高得点を得るためには、単に排出量を報告するだけでなく、気候変動を経営課題として捉えトップマネジメントが関与していること、リスク・機会を定量的に分析して戦略を構築していること、そして野心的かつ具体的な排出削減目標を掲げ着実に行動していることを示す必要があります。日本においては、CDP気候変動プログラムへの対応が大企業を中心に急速に広がりました。CDPは2022年に東京証券取引所プライム市場の全上場企業に気候変動情報の開示を要請しており、その結果、同年には日本企業1,800社超が気候変動質問書の対象となりました。これは投資家からの強い要請に基づくもので、事実上主要企業にとってCDPへの気候変動情報開示は標準的な責務となりつつあります。企業側もこれに応じ、統合報告書やサステナビリティレポートでTCFDに準拠した気候情報開示を行う際に、CDP質問書を活用するケースが増えています。CDPへの回答は任意とはいえ、回答しないままでいると投資家からの評価や国際的な信用に影響しかねない状況となってきています。
以上のように、CDPの気候変動プログラムは企業の気候対応力を多面的に評価する枠組みであり、国際的に高い信頼性を持っています。次章以降では、このプログラムに企業が対応する上で重要となる排出量の測定・報告、求められる気候変動対策の内容、そして先進企業の事例について詳しく見ていきます。
2. 温室効果ガス排出量の測定と報告の重要性
「測定できないものは管理できない」というマネジメントの原則があるように、気候変動対策においてまず重要なのは自社の温室効果ガス(GHG)排出量を正確に測定し報告することです。
GHG算定
CDP気候変動質問書でも序盤の設問で、事業活動に伴うGHG排出量(スコープ1: 直接排出、スコープ2: 間接排出〈購入電力由来〉、スコープ3: サプライチェーンなどその他間接排出)の算定結果と算定方法について詳細な開示が求められます。多くの国ではGHG排出量の算定基準としてGHGプロトコルが採用されており、CDPでもこれに準拠した報告が推奨されます。
企業にとってGHG排出量の測定は、自社の気候変動への影響を定量化する作業です。これにより、どの事業所・工程・製品が最も排出量に寄与しているか(エミッションホットスポット)が把握でき、効果的な削減策の立案につながります。例えば製造業であれば、工場ごとのエネルギー消費量と排出係数を掛け合わせてスコープ1・2排出量を算定し、物流や社員出張、調達原材料のライフサイクル排出などはスコープ3として算定します。排出量算定には各種データの収集が必要ですが、CDPに回答するためのプロセスを構築することで社内のデータ管理体制が整備される副次効果もあります。CDPへの報告においては、過去数年分の排出実績や将来見通しも含めて開示することが望ましいでしょう。年ごとの排出量の増減傾向を示し、その変動要因(生産高の変化、削減施策の効果、事業範囲の変更など)を説明することで、単年度の数字だけでは見えないストーリーが伝わります。
第三者保証
また、可能であればGHG排出量に関する第三者検証を受け、その結果を報告することが信頼性向上につながります。外部検証済みであることはCDPスコア上もプラスに働きます。特筆すべきは、CDPからの要請により日本の主要企業のGHG開示が飛躍的に進んだ点です。前述のとおり2022年には東証プライム全企業にCDP回答要請がなされ、実際に日本企業1985社がCDPに気候変動情報を報告しました(回答率約60%程度)。この動きに合わせて、多くの企業が自社の排出量算定を初めて実施したり、範囲をスコープ3まで拡大するようになりました。例えばサプライヤーや製品使用段階での排出(スコープ3)情報は以前は把握が進んでいませんでしたが、CDP回答準備を契機に算定する企業が増えています。こうした定量データの網羅的な開示は、CDPスコアの土台であり、気候変動対策の出発点でもあります。
高まる対応ニーズ
さらに、日本国内では金融商品取引法に基づく「プライム市場企業のサステナビリティ報告の充実」方針などにより、GHG排出量開示の重要性が増しています。企業がCDPを通じて排出量を開示することは、自社の気候変動対応力を示すと同時に、投資家とのコミュニケーション基盤を築くことにもなります。実際、CDPの排出量データはBloombergや日経などの金融情報プラットフォームにも提供され、投資家は個別企業の排出トレンドを容易に参照できるようになっています。
このように、GHG排出量の測定・報告は企業の説明責任の観点からも不可欠であり、CDPはその標準的手法を提供していると言えます。要約すると、正確かつ包括的なGHG排出量の算定と開示は、CDP気候変動対応の第一歩です。これなくしては次のステップ(リスク評価や戦略策定)も議論できないため、各企業は社内外のデータを集約し、年次で更新可能なGHGインベントリを整備していく必要があります。その上で、次章で述べるような具体的対策を講じ、それらをCDPで報告していくことになります。
3. CDPが求める気候変動対策とは
CDPの評価基準を見ると、単に情報開示するだけでなく、企業がどのような気候変動対策を実施しているかが重視されています。では具体的に、CDPが高く評価する気候変動対策とはどのようなものなのでしょうか。本節では、企業が取るべき主な対策をいくつかのカテゴリに分けて説明します。
温室効果ガス排出削減のための取り組みで最も基本的な対策は、GHG排出そのものを削減する行動です。
企業活動に伴うCO₂等の排出を減らすため、以下のような施策が考えられます。
エネルギー使用の低炭素化
工場やオフィス、店舗等で使用する電力や熱エネルギーを、できる限り低炭素なものに転換します。具体的には、再生可能エネルギー電力への切替(自家発電やPPA契約の活用、グリーン電力証書の購入など)や、ボイラー燃料を重油・石炭からバイオマスや天然ガスに転換すること、設備の電化(化石燃料直接燃焼から電気への置換)などがあります。資生堂は事業運営で使用する電力を100%再生可能エネルギーにする目標を掲げ、RE100に加盟して国内外の拠点で再エネ導入を加速させています。また花王はスペイン工場にバイオマス熱利用プラントを新設するなど、工場エネルギーの脱炭素化を進めています。こうしたエネルギー源転換は排出削減の即効性が高いため、CDPでも積極的な事例として評価されます。
省エネルギーと効率向上
生産工程やオフィスのエネルギー効率を高める投資も重要です。高効率な設備導入(LED照明、インバーター制御、最先端の省エネ機器への更新)、工程の最適化、断熱・空調改善などによって単位生産あたりのエネルギー消費を削減します。省エネはコスト削減にも直結するため、ビジネス上のメリットも強調できます。CDPでは、エネルギー効率化の取り組み件数や投資額、その結果削減できたCO₂量などを報告する欄があり、具体例を挙げて回答することで積極的にアピールできます。例えば「全社で〇〇件の省エネプロジェクトを実施し、年間△トンのCO₂削減を達成した」等の情報です。
製品・サービスの低炭素化
自社の製造プロセスだけでなく、提供する製品やサービスそのものを低炭素型に革新することも、有力な気候変動対策です。自動車メーカーであれば電気自動車(EV)や燃料電池車の開発・販売拡大、住宅メーカーなら断熱性能の高い住宅やZEH(ネットゼロエネルギーハウス)の提供、化学メーカーなら製品ライフサイクル全体で排出を抑える新素材の開発、といった具合です。積水ハウスは住宅のZEH化を強力に推進し、2023年以降自社が供給する分譲マンションは全てZEH仕様とするなど、製品そのもののエネルギー効率を大幅に高めました。このような事業戦略上の取組みは、企業自らの排出削減だけでなく顧客側の排出(スコープ3カテゴリ11「製品使用による排出」)削減にも寄与するため、CDP回答上もハイライトすべきポイントです。
オフセットと除去
自社努力で削減困難な排出については、カーボンクレジットの購入や植林などで相殺(オフセット)することも選択肢です。ただし、現在のCDP評価ではオフセットよりも自社排出の実質削減を優先する姿勢が鮮明です。とはいえ長期的にはダイレクトエアキャプチャーやBECCSのような除去技術も含めた対策が求められるでしょう。現時点ではカーボンニュートラル製品の提供やJ-クレジット活用などを行う企業は、その旨を回答に記載して透明性を確保することが大切です。
以上のような直接的排出削減策に加え、排出削減目標の設定とその管理もCDPが重視するところです。企業は短期・中期・長期のGHG削減目標を設定し、それが科学的に十分な水準かを問われます。前述のとおり、SBT(Science Based Targets)イニシアチブから1.5℃水準で認定を受けている目標であれば、CDP評価上も高く評価されます。資生堂は2030年に向け全バリューチェーンでのCO₂大幅削減というSBT目標を設定し、花王も2040年カーボンゼロ・2050年カーボンネガティブという極めて野心的な長期目標を掲げています。このような目標の有無・水準と、その進捗(毎年の実績値)は明確に報告しましょう。
4. 気候変動リスクへの適応とレジリエンス強化
気候変動対策は排出削減だけでなく、気候変動による影響への適応(適応策)も含まれます。CDP質問書でも、気候変動が企業にもたらすリスクと機会についての設問があり、それぞれに対する対応策を問われます。企業が取るべき適応策の例としては以下があります。
物理的リスクへの対策
気候変動に伴い増加しつつある自然災害や異常気象への備えです。具体的には、工場やオフィスのハード面での災害対策(洪水リスクのある拠点に防波堤や排水設備を設置、高温対策として空調能力増強 など)、事業継続計画(BCP)の策定と訓練(各種災害シナリオに対応したBCPを整備)、サプライチェーン代替ルートの確保(特定地域の災害で原料供給が滞らないよう複数国から調達)などが挙げられます。例えば食品メーカーが気候変動で原料作物収量が不安定になるリスクに対し、原産地の多様化や気象に強い品種への転換を進める、といった戦略も適応策です。CDPでは、特定したリスクごとに対策を記載する欄がありますので、「洪水リスク:工場周囲の排水能力向上工事を実施」「熱波リスク:サーバールームに予備電源と高性能空調を導入」等、リスクに紐付けて具体策を書くと説得力が増します。
規制・制度リスクへの対応
炭素税の導入や環境規制の強化といった移行リスクに対して、法規制の動向を注視し予め対策をとることも必要です。例えばEUのCBAM(炭素国境調整メカニズム)に対応するため製品あたり排出原単位を下げておく、国内で排出量取引制度が始まってもコストを緩和できるように省エネ投資を進めておく、などです。また、気候関連の開示規制(金融庁の有価証券報告書での開示義務化など)が進む中で、それに先んじてTCFD報告を充実させておくことも適応策と言えるでしょう。実際、日本企業の多くが既にTCFD提言への賛同を表明し、気候リスクの開示に取り組んでいます。CDPへの回答内容はTCFD報告とも共通するため、CDPで高評価を得る企業は概ねTCFD開示においても充実した内容となっています。
気候変動に伴う機会の活用
リスクだけでなく、ビジネス機会の側面も検討が必要です。例えば、省エネ製品や再エネビジネス市場の拡大、他ニーズから生まれる新サービスなどは企業にとって成長機会となり得ます。CDP質問書でも、気候変動に関連するビジネス機会を特定し戦略に組み込んでいるか問われます。自社の強みが活かせる領域で積極的にソリューション提供を行っている場合(例えば空調メーカーが高効率冷房システムで市場拡大を図る等)、それを明示することで前向きな適応姿勢を示せます。
以上の適応策についても、定量的な裏付けがあると評価が高まります。例えば「当社はX℃気温上昇シナリオを分析し、50年時点で洪水リスクによる年間損失が○億円になる可能性を特定。それに対処すべく5億円を投じて防災インフラを強化し、予想損失を△%低減する計画を立てている」などと書ければベストです。難しい場合も、リスクと対応策を漏れなく列挙し、進捗(何%完了など)を示すと良いでしょう。
こうしたリスク対応力・レジリエンスの高さは、投資家にとって企業の将来安定性を判断する重要情報であり、CDPでも高ポイントにつながります。
5. ガバナンスと社内体制の整備
気候変動への取り組みを有効に進めるには、組織横断的な体制とトップのコミットメントが不可欠です。CDPの質問書でも、気候変動に関するガバナンス体制を問う項目が複数設けられています。ここで評価されるポイントをまとめると以下の通りです。
取締役会レベルの関与
気候変動課題に対して、取締役会や経営会議が監督責任を負っているか。例えば、年に何回か経営陣が気候変動戦略やリスク評価の報告を受け審議しているか、特定の取締役にその責務が割り当てられているか等です。最高経営責任者(CEO)や取締役会長が自ら気候戦略を主導している場合や、取締役会にサステナビリティ委員会が設置されている場合は明記しましょう。
経営層の報酬とKPI
気候変動目標の達成状況が経営層や従業員の評価・報酬制度に組み込まれているか。例えば、「役員報酬の〇%はGHG削減目標の達成度合いに連動」といった仕組みがあれば記載します。これにより経営陣のコミットメントの強さを示せます。
専門部署・委員会の設置
社内に気候変動対策を推進・統括する部署や委員会があるか。環境担当部署やサステナビリティ担当役員の下に、温暖化対策プロジェクトチームがある、といった情報を提供します。また子会社や海外拠点も含めグループ全体で統一方針を敷いている場合も伝えます。
従業員や組織文化への浸透
気候変動への取り組みが社内で共有され、人材教育や目標管理に組み込まれているかも間接的に評価されます。社員研修で気候変動やSDGsを扱っているか、社内アイデアコンテストで脱炭素の提案を募った経験があるか、といったエピソードも自由記述で触れることができます。
ガバナンス面の充実は定性的な事項ですが、トップメッセージの有無や社内規程の制定など、できるだけ客観的に示せるものを回答に盛り込むと良いでしょう。例えば「当社の取締役会は年2回、気候変動・環境戦略の審議を行っており、その概要は統合報告書で公開している」「CEOはパリ協定達成を支持する声明『Business Ambition for 1.5°C』に署名している」といった具体的事実は強力なアピールになります。資生堂の例では、気候変動緩和の取組みとしてSBT目標設定やRE100加盟を行い、さらに事業と気候・生物多様性の関連を分析したTCFD/TNFDレポートも開示していることを明示し、これらが同社のガバナンスと戦略に織り込まれている点を強調しています。結果として資生堂はCDP気候変動で2年連続Aリストに選定され、リーダーシップを発揮していると評価されました。
6. 先進企業の事例に学ぶ
CDP気候変動分野で高い評価を受けている先進企業の事例は、具体策を検討する上で大いに参考になります。
ここでは、日本企業の中から注目すべき取組みを行っている2社の例を紹介します。
積水ハウス株式会社 – 住宅業界における脱炭素経営の先駆者
積水ハウスは2023年、気候変動・森林・水セキュリティの3分野すべてでCDP最高評価のAを獲得し、国内住宅メーカーとして初のトリプルA企業となりました。同社の特徴は、主力事業である住宅供給において徹底した気候変動対策を組み込んだ点にあります。具体的には、建築する住宅のZEH(ネットゼロエネルギーハウス)化を推進し、2022年度には戸建住宅の93%をZEH仕様にするという驚異的な達成を遂げました。さらに2023年以降は、自社が供給するすべての分譲マンションをZEH化する方針を打ち出しています。ZEH住宅は居住時のエネルギー収支が実質ゼロとなるため、利用段階でのCO₂排出を大幅に削減できます。積水ハウスはこれにより、自社の顧客から生じる温室効果ガス排出(スコープ3)にも踏み込んだ対策を講じたことになります。また同社は早くから自社オペレーションの脱炭素化にも取り組み、2030年までに事業活動由来のCO₂排出を半減させる目標を掲げています。加えて、業界団体や国際イニシアチブにも積極参加し、建築分野の脱炭素化を主導する姿勢を示しています(例えば国連の「建築物における気候行動」アライアンスへの加盟など)。これら一連の戦略は、単なる環境対策に留まらず「低炭素住宅市場での競争優位獲得」という事業戦略と一体化しています。
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2024/20240206/
花王株式会社 – 製造業における統合的な環境リーダーシップ
花王は2019年から2022年まで4年連続でCDP気候変動・森林・水それぞれでA評価を獲得し、世界でも数少ないトリプルA企業の一つです。気候変動分野において注目すべきは、その長期ビジョンと包括的な施策です。花王は「2040年までに自社事業からの温室効果ガス排出をゼロ(カーボンゼロ)に、2050年までには吸収量が排出量を上回るカーボンネガティブを達成する」という壮大な目標を掲げています。この目標達成に向け、既に国内外の工場で様々な削減策を実行中です。例えば工場ボイラーでのバイオマス燃料利用により化石燃料使用を削減したり、製品包装ではプラスチック使用量を削減するため肉薄化した詰替えパウチを開発するなど、排出源ごとに具体策を講じています。同社の強みは、気候変動対策を単体でなく水・森林など他領域の取組みと関連付けて推進している点です。例えば気候変動分野で生まれた技術(洗剤の高濃度化と低温洗浄の実現)は、水使用量削減や消費者のエネルギー節約にもつながっており、総合的な環境価値を創出しています。また花王はシナリオ分析にも熱心で、気候変動シナリオに基づき自社の長期リスクと機会を分析し、それを元に具体的な数値目標やアクションプランを策定しています。このような科学的根拠に基づく計画とマルチステークホルダーへの配慮が評価され、花王は日本企業唯一の4年連続トリプルAという快挙を達成しました。花王のケースは、製造業における気候変動対策のお手本であり、製品開発・設備投資・サプライチェーン管理といったあらゆる経営資源を総動員して脱炭素と事業成長を両立させている点が示唆に富みます。
https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20240206-001/
以上の先進企業事例から、気候変動対策で成功している企業の共通点を整理すると、「大胆な目標設定」「事業戦略への組込」「技術革新の活用」「ステークホルダー協働」「透明性の高い情報開示」に集約できます。自社の状況に応じて取り入れられる要素は多いでしょう。CDPへの対応は単なる報告作業ではなく、自社の気候変動対策を見直し強化する契機となります。積水ハウスや花王のような企業に倣い、攻めの姿勢で気候戦略を展開することが、結果的にCDPスコア向上にもつながるのです。
7. CDPまとめ
CDPと気候変動への対応は、いまや多くの企業にとって実質的な報告義務に近い重みを持っています。しかし裏を返せば、それは企業が自らの気候変動対策を国際水準に高め、競争力強化につなげるチャンスでもあります。本記事で述べたように、温室効果ガス排出量の測定・開示、野心的な削減目標の設定、統合的なリスク・機会対応、そして経営戦略への組込みと組織体制の整備を進めることで、企業はCDPという枠組みの中で着実に評価を高めることができます。CDPのスコアリング基準は単なる評価指標に留まらず、企業が何をすれば環境経営の先進例となれるかを示すロードマップとも言えます。情報開示の質を高めることは、投資家や市場からの信頼獲得につながり、ひいては資金調達コストの低減やブランド価値の向上といった経済的メリットをもたらします。
また、気候変動対策の過程で生まれた技術やノウハウは新規事業の創出やコスト削減に資する場合も多く、中長期的な企業価値向上に直結します。実際、CDPからA評価を得る企業は、気候変動への対応力が高いだけでなく、経営全般にわたり先見性と持続可能性を備えていると見做され、株式市場でも良好な評価を受ける傾向が指摘されています。
最後に強調したいのは、CDPへの取り組みを「規制対応」や「外圧への順応」と捉えるのではなく、自社の変革を促すポジティブなドライバーと位置付ける視点です。社内の部門横断的な連携が深まり、環境データの整合性や一貫性が向上し、経営陣が長期視野でリスクと機会を議論するようになる――CDP報告を進める中で、このような企業文化の成熟が期待できます。それ自体が企業のレジリエンスを高め、ひいては新たなイノベーションの土壌を育むことにつながります。気候変動は企業経営において無視できない現実の課題です。CDPはその課題に真正面から向き合う企業をエンカレッジし、適切に評価する舞台を提供してくれます。企業はこの舞台を是非活用し、自社の強みを示すとともに弱点を洗い出して改善を図りましょう。そのプロセスを通じて、気候変動という人類共通の問題解決に貢献しつつ、企業としての持続的成長を実現する道が開けてくるはずです。CDPへの対応はゴールではなく、そのような未来への出発点と言えます。
引用
CDP 気候変動レポート 2023: 日本版
CDP 気候変動質問書スコアリング基準 2023年版
https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/009/502/original/CDP2023_Japan_Report_Climate_0319.pdf