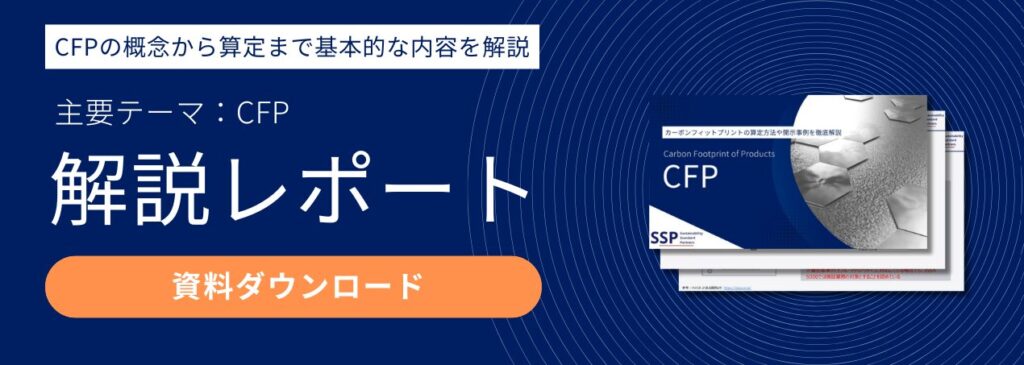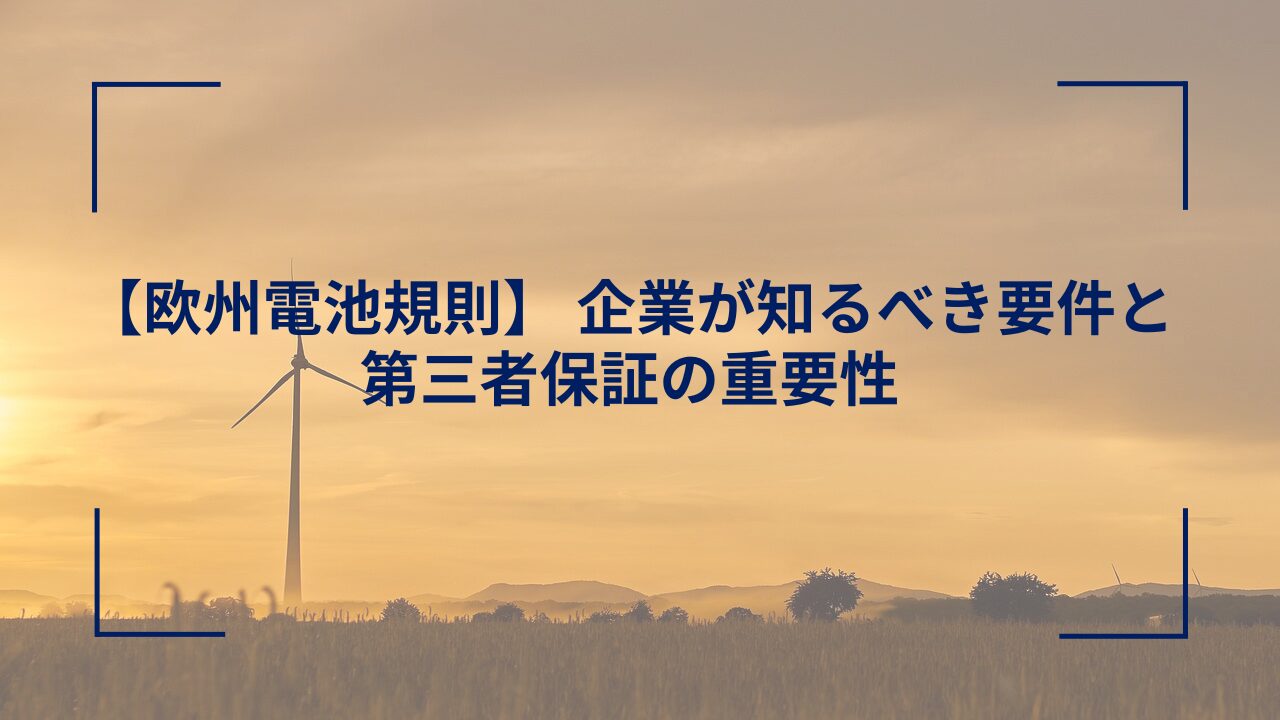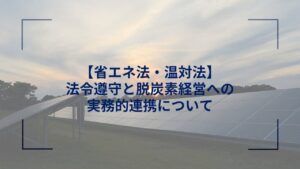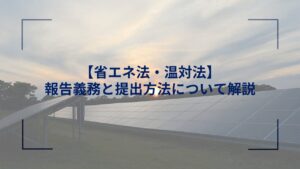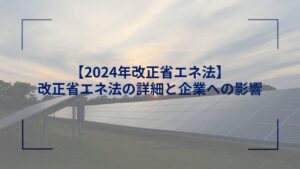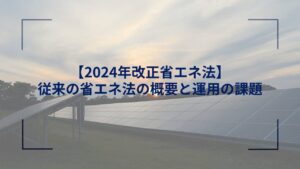欧州電池規則(European Battery Regulation)は、2024年2月に適用が開始されたEUの新しい規制であり、電池の製造から廃棄までの環境負荷削減や資源循環を目的としています。本規則は、カーボンフットプリント(CFP)の算定・報告義務、使用済み電池の回収・リサイクル義務、人権・環境デューデリジェンス(DD)の義務化、第三者保証(認証)の取得など、多くの厳格な要件を含んでおり、EU市場で電池や電池を搭載した製品を販売する企業に大きな影響を与えます。特に、2025年以降は段階的に規制が強化され、CFPの上限規制やリサイクル材料の使用義務が導入されるため、企業は早期の対応が求められます。
本記事では、欧州電池規則の概要、主要要件、企業が取るべき対応について解説します。


1. 欧州電池規則の概要と目的
欧州電池規則(European Battery Regulation)とは、EUが2023年8月に制定し、2024年2月から適用開始した新たな規則です。従来の電池指令を強化・拡張するもので、規模や所在地を問わずEU市場で流通するすべての種類の電池が対象になります。この規則の目的は、電池のライフサイクル全般にわたって環境負荷を最小限に抑えつつ、持続可能な電池生産と利用を促進することにあります。
具体的には、温室効果ガス排出量の削減や資源の循環利用を推進し、電池の生産・廃棄に伴う環境影響を低減することが狙いです。欧州電池規則はEUの「欧州グリーン・ディール」戦略の一環として位置づけられ、2050年までの温室効果ガス実質ゼロ(カーボンニュートラル)達成に貢献するものです。
また、自動車の電動化により電池需要が急増する中、電池の製造から廃棄まで一貫して環境配慮を求める法的枠組みを整備することで、サーキュラーエコノミー(循環経済)を実現し、欧州域内の資源効率向上や原材料調達リスクの低減も図られています。さらに、環境に優しい電池の開発と普及を促すことで、欧州の電池産業における競争力強化という経済的目的もあります。要するに、欧州電池規則は「電池の設計・製造から使用後の回収・再利用に至るまで」包括的に規制することで、持続可能なバッテリー産業への転換を目指したものです。そのため、規則に違反して要求事項を満たせない製品はEU市場で販売できなくなる可能性があり、欧州市場を対象とする企業にとって無視できない重要なルールとなっています。
規制強化の背景
今回の規制強化の背景には、電気自動車(EV)の普及拡大や再生可能エネルギー貯蔵の需要増大によって、電池の生産量と使用済み電池の排出量が今後飛躍的に増えると見込まれていることがあります。
もし電池の製造や廃棄が適切に管理されなければ、二酸化炭素排出や有害物質漏出などによる環境負荷が大きな問題となりかねません。EUはこうしたリスクに対処し、電池による環境影響を上流から下流まで総合的に抑制する必要性を感じていました。また、電池の原材料にはコバルトやリチウムなど一部の希少金属が含まれ、これらの資源調達に伴う人権侵害(例えば鉱山での労働搾取)や環境破壊も国際的な課題となっています。
欧州電池規則ではサプライチェーン全体での責任ある調達を義務付け、人権・環境デューデリジェンスの徹底を図ることで、持続可能で倫理的な供給網の構築を目指しています。
さらに、従来のEU電池指令(2006/66/EC)は主に電池の廃棄段階のみをカバーしており、製造時の炭素排出や使用材料の持続可能性などについての規定が不十分でした。加盟各国で規制のばらつきもあり、単一市場で公平な競争条件を確保する観点からも、新たな統一ルールが求められていたのです。
欧州電池規則は、こうした規制の隙間を埋め、電池の生産・使用・廃棄までを網羅する包括的な要件を導入することで、環境面だけでなく社会面・市場面での課題にも対応しています。
企業にとっての影響は甚大で、EU市場で電池や電池を搭載した製品を販売する企業は、この規則に適合するために製品設計や製造プロセス、サプライチェーン管理における大幅な見直しが必要となります。例えば、自社製品のカーボンフットプリントを計測して報告する体制の構築、原材料調達先の監査、使用済み電池の回収ネットワークの整備など、多岐にわたる取り組みが求められます。

2. 欧州電池規則の主要要件
欧州電池規則には企業が遵守すべき多岐にわたる要求事項があります。
特に強化された主要要件として、「カーボンフットプリントの算定・報告」「リサイクルと循環経済の推進」「第三者保証(認証)の取得」の3つが挙げられます。以下、それぞれについて概要を解説します。
カーボンフットプリント(CFP)とは
カーボンフットプリント(CFP)とは、製品やサービスのライフサイクル全体(原材料の採掘・調達から製造、流通、廃棄・リサイクルまで)で排出される温室効果ガス(CO₂換算)の総量を表したものです。欧州電池規則では、このCFPの算定と申告が一定規模の電池に対して義務付けられました。
具体的には、電気自動車用電池や一定容量以上の産業用蓄電池について、製造工場ごとの各電池モデルごとにCFPを算出し、その値を第三者検証機関(認証機関)によって検証されたうえで申告(報告書の提出)する必要があります。
なお、電池の使用段階(例えばEV搭載後の走行時に生じる排出)はメーカーの直接的な管理範囲ではないため、CFP計算から除外することが認められています。これは、充電時の発電由来の排出など使用時要因は電池メーカーに帰責させないという配慮です。CFP申告は段階的に導入され、例えば電気自動車(EV)用電池では2025年2月から算定・申告義務が開始される予定です。
まずは情報開示(カーボンフットプリントの報告)を義務付け、その後2026年以降にCFP値の性能クラス分けが導入され、最終的には2028年2月18日以降にCFPの上限値(しきい値)が設定され、この上限を超える高炭素な電池はEU域内で販売できなくなる見込みです。つまり、将来的に一定以上にCO₂排出の大きい電池は市場参入が禁止されることになり、企業は計算と報告だけでなく実際に排出削減を達成することが求められます。
リサイクルとサーキュラーエコノミー
欧州電池規則では、電池のリサイクルと循環型経済(サーキュラーエコノミー)の推進が重要な柱となっています。具体的なリサイクル関連要件は主に次の2点です。
使用済み電池の回収・リサイクル義務
製品寿命を終えた電池を確実に回収し、適切にリサイクルするために、メーカー(電池を市場に出す者)には回収率の達成義務が課されます。
例えば、ポータブル(一般家庭用の小型)電池の場合、加盟各国において2027年末までに少なくとも63%、2030年末までに73%という高い回収率目標が設定されています。
また、新たに定義された「軽輸送手段(LMT)用電池」(電動自転車や電動スクーター等に使われる電池)についても2028年末までに51%、2031年末までに61%の回収率目標が定められました。
企業はこれらの目標を達成するため、販売した電池の回収スキームを構築し、消費者からの回収・リサイクル体制を整備する義務があります。回収した使用済み電池は、専門のリサイクル業者に引き渡し、適切な処理と資源の回収を行わなければなりません。さらにリサイクル工程における効率向上も求められており、例えばリチウム電池中のリチウム回収率50%(2027年末まで)、80%(2031年末まで)といった素材ごとのリサイクル効率目標も設定されています。
これにより、電池に含まれる貴重な金属資源をできる限り回収・再利用する循環ループの実現が図られています。
再生資源の利用(リサイクル材料の含有率)義務
リサイクルで回収した資源を新たな電池に積極的に活用することも義務付けられました。特に電気自動車用、産業用、及び自動車用(SLI)バッテリーについて、電池の活物質(電極材料)に含まれる特定金属についての再生材料の最低使用率が段階的に導入されます。
例えば、2031年8月以降に製造される電池では、コバルトの16%以上、鉛の85%以上、リチウムの6%以上、ニッケルの6%以上をリサイクル由来の資源で賄うことが義務となります。これらの割合を満たしていることを技術文書で証明し、製品に添付することが必要です。
さらに将来的には目標値が引き上げられる計画で、例えばコバルトは2035年以降26%に引き上げられる予定です。
このように、新品電池へのリサイクル材の使用をメーカーに義務付けることで、資源循環の「出口」(再資源の需要創出)も確保し、リサイクル市場の活性化と資源調達の持続可能性向上を狙っています。以上のように、欧州電池規則は電池の「使用後を見据えた設計」を促しています。製品設計段階から将来の回収・再利用を考慮し、有害物質の含有削減(例えば水銀やカドミウムの使用禁止/低減)や、電池の取り外し・交換容易性の確保(内蔵電池であっても消費者が容易に取り外せるように設計する義務)なども求められています。これらの要件は、電池を含む製品全体の循環寿命を延ばし廃棄物を削減する、サーキュラーエコノミー実現のアプローチといえます。

3. 欧州電池規則における第三者保証の重要性と対応方法
欧州電池規則の特徴として、企業が提出・開示する各種情報に対し第三者保証(Third-Party Assurance)を受けることが義務付けられている点が挙げられます。第三者保証とは、企業自らの自己申告だけでなく、独立した検証機関(欧州委員会に通知された認定機関、いわゆるNotified Body)によってデータやプロセスの信頼性を確認・証明してもらうことです。本規則では、以下のような項目について第三者による検証が要求されています。
カーボンフットプリント(CFP)宣言
前述のとおり、CFPの算定結果は第三者検証機関による証明が必要です。具体的な算定方法やデータの正確性について、公正な立場の機関がレビューし、妥当であると認められなければなりません。
サプライチェーン・デューデリジェンス(DD)報告
原材料の調達に関する人権・環境デューデリジェンスについても、第三者機関の検証を受けたレポートを作成し、公表する義務があります。
2025年8月18日以降は、このサプライチェーンDDが本格施行され、企業は自社の管理システムに組み込まれた方針とその実施状況について、認定機関による監査・認証を受ける必要があります。
再生材料含有率の証明
リサイクル材料の含有義務についても、その達成状況を裏付ける技術文書等に第三者の検証を受けた証明を付すことが求められています。製品に付与するラベルや電池パスポートの情報も、信頼性確保の観点から必要に応じて検証を経ることになるでしょう。
第三者保証が重要視されるのは、企業の提供する環境・サステナ情報の信頼性を高め、市場における「グリーンウォッシュ(虚偽の環境配慮アピール)」を防ぐためです。独立機関のチェックを経たデータのみが公式な環境情報として認められることで、ルール遵守企業と不遵守企業の差別化が明確になり、公平な競争条件が保たれます。企業側にとっては手間とコストが増えるものの、認証取得によって自社製品の適合性を対外的に証明できるメリットがあります。
対応方法としては、企業はまず各種要件に適合するための内部体制を整えた上で、早めに認証機関との連携を図ることが重要です。
例えば、CFP算定ならライフサイクルアセスメント(LCA)の専門家やツールを活用して数値を算出し、その結果をISO標準等に従って文書化します。そして公認の検証機関にレビューを依頼し、認証書や検証報告書を発行してもらいます。サプライチェーンDDであれば、サプライヤーからの情報収集やリスク評価プロセスを文書化し、第三者監査を受けて適切に運用されていることの証明を取得します。
これらの証明書類は製品の技術文書の一部として保存するとともに、一部情報は「バッテリーパスポート」や企業サイトを通じて公開することも義務付けられています。なお、欧州電池規則の遵守は製品のCEマーキング要件とも連動しています。2024年8月から、電池製品に新規則適合のCEマーキングを付すことが必要となり、特に大型電池では第三者認証機関が関与した適合評価を経ることが要求されます。そのため、日本企業も早めに欧州の認証機関や試験所とコンタクトを取り、自社製品の適合証明に抜かりがないよう準備を進めることが肝要です。
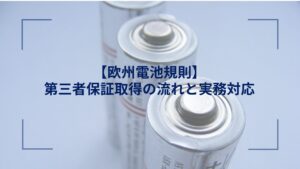
4. 欧州電池規則で企業が取るべき対応
欧州電池規則への対応は、単に環境部門だけでなく、製品開発、調達、生産管理、品質保証、法務など企業全体で取り組むべき課題です。ここでは、企業が着手すべき箇所を紹介します。
コンプライアンスチェックリスト
以下に、欧州電池規則への準拠のため企業が取るべき具体的アクションをまとめます。
製品分類の確認
自社が扱う電池が規則で定義されたどのカテゴリ(ポータブル、LMT、SLI、産業用、EV用)に該当するかを確認しましょう。カテゴリによって適用される要件やスケジュールが異なるため、まず影響範囲を明確にすることが重要です。
CFP算定と削減計画
対象となる電池について、ライフサイクル全体のCO₂排出量データを収集・算定する仕組みを構築します。算出には原材料や部品のサプライヤーから提供される環境データ、工場のエネルギー使用量、輸送時の排出量などを網羅的に集める必要があります。算定結果は第三者検証を受け、期限までに当局へ申告できるようにします。合わせて、将来的なCFP上限規制に備え、再生可能エネルギーの利用拡大や省エネ施策など排出削減計画も策定します。
サプライチェーン・デューデリジェンス体制整備
コバルトやリチウムなど指定鉱物の調達先について、人権・環境リスクを評価する社内手続きを確立します。サプライヤーに対するアンケート調査や現地監査を実施し、リスクが高い場合の是正策も準備します。これらの取り組みをデューデリジェンス方針として文書化し、2025年8月までに第三者認証を受けて運用を開始できるようにします。
ラベル表示・情報開示の準備
電池に表示すべき項目(容量、化学成分、有害物質含有、分別回収シンボル等)や、付属の技術文書/電池パスポートに記載すべき情報(モデル識別子、製造地、CFP値、リサイクル含有率など)を洗い出します。欧州委員会が策定する統一ラベル要件に合わせ、必要なデータを製品やパッケージ、デジタルプラットフォームに掲載できるよう社内システムを整備します。特にQRコード経由でアクセスされるデジタル電池パスポートには多岐にわたる情報を登録する必要があるため、関連部署で協力してデータ管理基盤を構築しましょう。
リサイクル計画と拠点構築
販売後の電池回収について、各販売国で適切な回収スキームに参加または構築する計画を立てます。既存の業界団体の回収ネットワークへの加盟や、自社独自のリサイクル拠点設置の検討も含め、回収率目標(例:63%/2027年)を達成するためのロードマップを策定します。併せて、回収した電池を効率よくリサイクル処理できるパートナー企業(リサイクル事業者)との連携を深め、将来的なリサイクル効率や再資源化率の報告義務にも対応できる体制を作ります。
技術文書と認証記録の整備
上記の各種データや証明書を統合した技術文書(Technical Documentation)を整備します。これには、CFP宣言書、デューデリジェンス報告書、リサイクル含有率の検証書類、性能試験結果、ラベル表示例などが含まれます。技術文書は規則の要求に従って一定期間保存し、必要に応じて監督当局に提出できるようにしておきます。また、CEマーキングの適合宣言書も忘れずに用意します。
以上のチェックリストを参考に、自社のどの部分が不足しているかを点検し、早急にギャップを埋めることが求められます。
5. 欧州市場での競争力を維持する方法
欧州電池規則への対応はコスト要因であると同時に、企業にとって競争力維持・向上のチャンスともなりえます。規則遵守を単なる義務ではなく戦略的メリットに転換するためのポイントをいくつか挙げます。
環境対応をブランド価値
規則に適合した電池は「低炭素・高持続可能性」という付加価値を備えています。自社製品がCFP低減やリサイクル材料高含有など最先端の環境基準を満たしていることを積極的にアピールしましょう。欧州の消費者や自動車メーカーはサプライヤーに対し環境性能を重視する傾向が強まっており、この点で先行すれば競合との差別化につながります。実際、欧州市場ではサステナビリティに優れたバッテリーはプレミアム商品として評価される可能性があります。
サプライチェーンの強靭化
規則対応を進める過程で、サプライヤーの見直しや関係強化が図られます。例えば、認証を取得した信頼性の高い原材料供給源を確保できれば、将来的な資源制約や価格変動リスクに強い体制が築けます。また、リサイクルによる二次資源の活用は、長期的には新規資源調達コストの低減や供給安定化にも寄与します。こうした循環型の供給網をいち早く構築することで、原材料調達競争において有利なポジションを得られるでしょう。
技術革新と製品改良
規則順守には電池そのものの改良も不可欠です。例えば、CFPを削減するにはエネルギー効率の高い製造設備への投資や、電池のエネルギー密度向上(少ない材料で高性能を出す)による間接排出削減が求められます。また、耐久性要件への対応で電池寿命が延びれば、ユーザーにとっても魅力的な製品となり、市場競争力が高まります。規制対応として行った技術革新が結果的に製品品質を高め、新たなビジネス機会(例えば長寿命バッテリーの提供や、使用済み電池の二次利用サービスなど)を創出することも期待できます。
法規制の先取り戦略
欧州電池規則は世界でも先進的な環境規制であり、他の地域でも将来的に類似のルールが導入される可能性があります。実際、バッテリーのサステナビリティ確保はグローバルな課題であり、中国や北米、日本でも政策議論が進んでいます。欧州規則への適合プロセスを通じてノウハウを蓄積しておけば、他地域での規制強化にも柔軟に対応できるでしょう。その意味で、欧州対応をグローバル展開への投資と位置づけることができます。
このように、企業努力次第で「コスト」から「競争優位」へと逆転させることが可能です。重要なのはトップマネジメントの理解と全社的な取り組みです。環境規制対応を経営戦略の一部として組み込み、プロジェクトマネジメントを徹底することで、欧州市場でのレジリエンスと成長を両立させることができるでしょう。

6. 欧州電池規則のまとめと今後の展望
欧州電池規則は、電池産業における包括的な環境・サステナビリティ規制です。その要求水準は高く、企業にとって挑戦的ではありますが、同時に持続可能なビジネスモデルへの転換を促す強力な要素でもあります。日本を含む関連企業は、この規則の趣旨を正しく理解し、早期から準備を進めることでリスクを最小化しつつ新たな機会を捉えていく必要があります。
今後の展望として、まず規則の詳細運用が段階的に明らかになっていくでしょう。欧州委員会は今後、具体的な実施規則(Implementing Act)やガイダンスを発出し、CFP算定方法の標準化や電池パスポートの運用仕様などを定めていきます。企業はそうした最新情報をウォッチし、必要に応じて社内方針や計画をアップデートすることが重要です。また、技術面ではより環境負荷の少ない次世代電池(例えば全固体電池やナトリウムイオン電池など)の開発も規制対応の文脈で加速する可能性があります。
規則が要求するリサイクル性や耐久性を高いレベルで満たす革新的な製品が市場に登場すれば、業界構造にも変化が生じるでしょう。各企業は、自社の研究開発戦略と規制の方向性とを照らし合わせ、将来を見据えた投資判断を行うことが求められます。最後に、欧州電池規則は「持続可能な産業への転換」という不可逆的な潮流を象徴しています。本規則への対応を通じて培った環境対応力こそが、中長期的には企業価値を左右する時代となることが予想されるため、規則の網羅的な解説と企業視点でのポイントを押さえたうえで、自社の戦略に落とし込み、強靭な企業経営を目指す必要があります。
引用元
Regulation (EU) 2023/1542(正式文書全文)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542
欧州委員会:バッテリー・蓄電池に関する解説ページ
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries-and-accumulators_en
Proposal for a Regulation on batteries(COM/2020/798)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
旧バッテリー指令(Directive 2006/66/EC)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
JETRO(日本貿易振興機構)
https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu
経済産業省(METI)
https://www.meti.go.jp