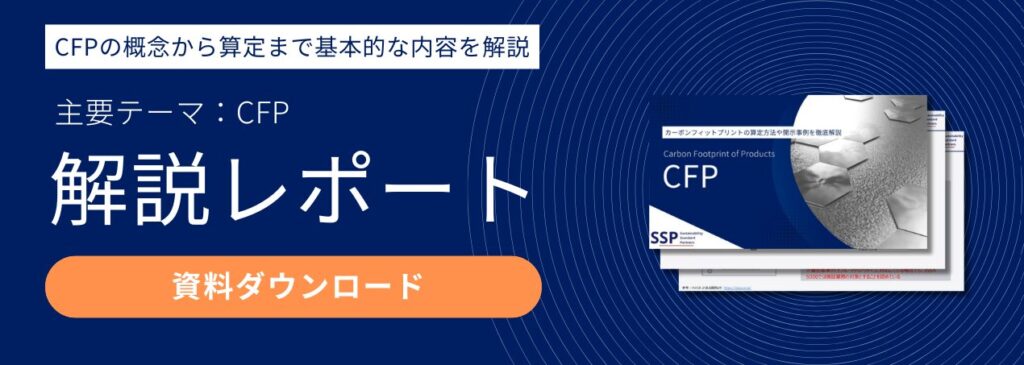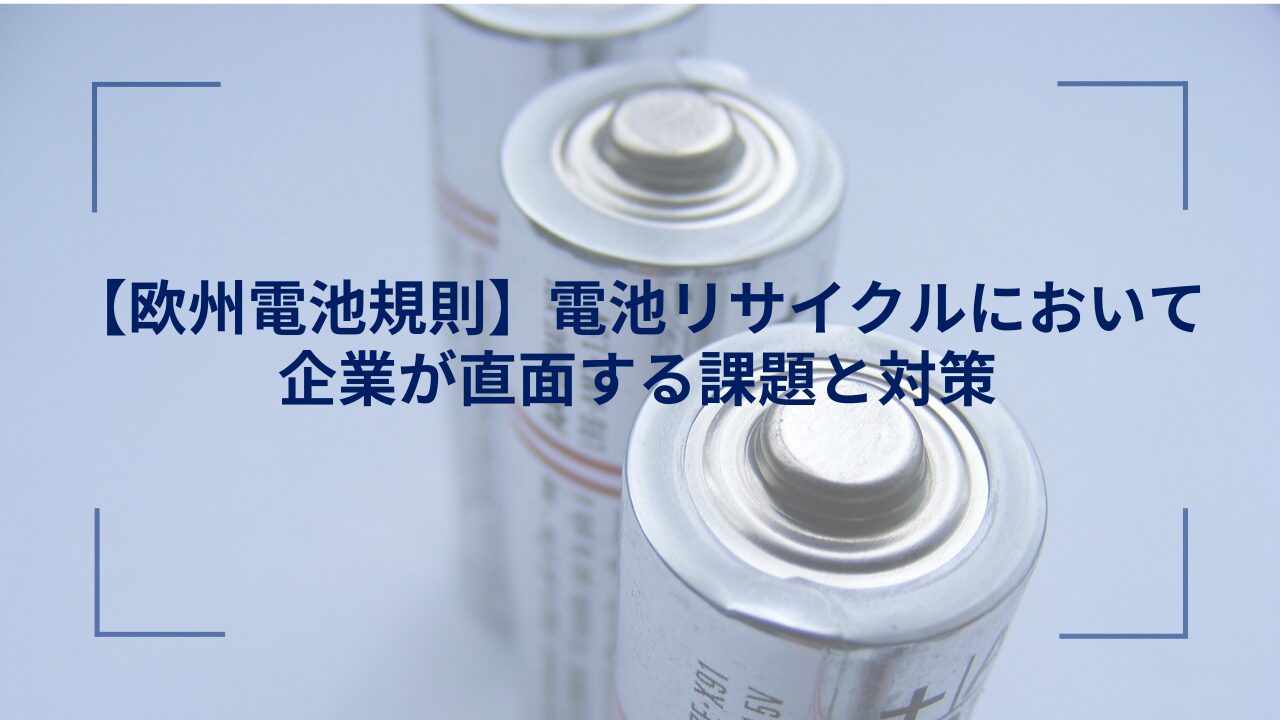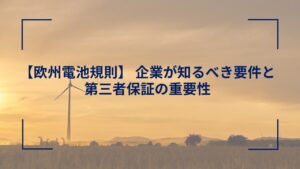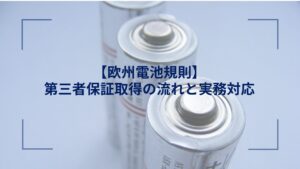欧州電池規則は、電池のライフサイクル全体での環境負荷を低減するため、使用済み電池の回収義務、リサイクル効率・再資源化率の目標設定、再生材の最低使用率の義務化を企業に求めています。企業は「拡大生産者責任(EPR)」の考えのもと、回収ネットワークの整備やリサイクル業者との連携が不可欠となります。
また、NorthvoltやUmicoreなどの先進企業は、自社リサイクル施設の設置やクローズドループの資源循環システムを構築し、規則対応を競争力に変えています。
本記事では、欧州電池規則のリサイクル要件と企業が直面する課題、対応策や成功事例を解説します。


1. 欧州電池規則におけるリサイクル要件
欧州電池規則は、電池のリサイクルに関してこれまで以上に強い要求を強いています。その要件は、大きく分けて「使用済み電池の回収義務」と「リサイクル効率・再資源化率の目標設定」にまとめられます。
使用済み電池の回収率目標
規則では各国ごとに、メーカーによる使用済み電池の回収率(collection rate)目標が設定されました。
例えばポータブル電池(小型一次電池や家庭用充電池)では、2027年末までに各国で63%、2030年末までに73%の回収率を達成することが義務付けられています。
これは販売量に対する回収量の比率で計算されます。また、新たに規定されたLMT用電池(電動自転車等)の回収についても、2028年末まで51%、2031年末まで61%の目標値が導入されました。
この他、自動車搭載のSLI電池や産業用電池も従来同様にメーカーが回収の責任を負い、高い回収率維持が求められます。これらの目標値は従来のEU電池指令より大幅に引き上げられており、企業は販売後の製品回収体制を強化しなければ達成は困難です。
リサイクル効率および材料の再資源化率
回収した使用済み電池をどこまで有効利用できたかを示す指標として、「リサイクル効率」(Recycling Efficiency)と「マテリアルリカバリー率」(Materials Recovery Rate)が規則で定められました。
リサイクル効率とは、投入された廃電池の質量に対し、得られた二次原料(再利用可能な材料)の質量の割合を指します。例えば、100kgの使用済みリチウムイオン電池を処理して50kgの金属類を回収できたら効率50%です。
規則ではリチウムイオン電池に対し、2025年末までにリサイクル効率50%、2030年末までに80%という目標が設定されました。
また鉛蓄電池は80%(2030年まで)、ニッケルカドミウム電池は80%(2025年まで)といった数値が挙げられています。さらに材料回収率として、特定の有価金属についてどれだけ回収すべきかも指標化されています。例えばコバルトやニッケル、銅は2027年末までに90%、2031年末までに95%を回収する、といった非常に高い目標を示しています。
これらはリサイクル事業者に直接適用される目標ですが、メーカーも自社の電池がそのように高効率でリサイクルされるよう、適切なリサイクル手法を採用する責任があります。
再生材料の最低使用率義務
リサイクルで得られた材料を新しい電池に使う義務については前章で述べた通りですが、これもリサイクルを促進する要件の一つです。2031年以降、電池製造時に一定割合の再生材を使用することになるため、メーカーは質の高い再生材を安定供給してもらえるよう、リサイクル業界との連携を強める必要があります。
2. 企業の責任とリサイクルプロセス
上記のリサイクル要件を受け、企業(電池メーカーや電池を製品に組み込んで販売するメーカー)は「拡大生産者責任(EPR: Extended Producer Responsibility)」の考え方に基づき、使用済み電池の回収とリサイクルに主体的に関与することが求められます。
1. 回収ネットワークの構築
メーカーは販売した電池が使用済みになった際に適切に回収されるよう、回収スキームを構築する義務があります。これは各国で異なる方法が取られますが、一般的には販売店回収(販売店が使用済み電池を引き取る)、自治体拠点回収(市町村のリサイクルボックスに消費者が投入)、郵送回収(回収キットを消費者に送り返送してもらう)などの手法が組み合わされます。メーカー単独で行うのが難しい場合、多くは業界団体や専門の共同回収システム(Producer Compliance Scheme)に参加し、費用を分担して回収インフラを整備します。
企業の責任はこうした仕組みに拠出金を払うだけでなく、消費者に対して「捨てずに回収に出してください」と促す啓発や、容易に回収に出せる工夫(例えば着払い回収サービス)を提供することも含まれます。
2. 分別と安全処理
回収された電池は種類ごとに分別されます。リチウムイオン電池は発火の危険があるため絶縁テープを貼るなど安全措置がとられます。一次電池(使い切り電池)と二次電池(充電池)は別々にされ、さらに化学種類(リチウムイオン、ニッケル水素、鉛蓄電池等)やサイズごとに分類されます。この分別は効率よくリサイクルする前提として重要です。企業は回収業者やリサイクル業者に適切な情報提供(自社電池の化学組成や安全上の注意点など)を行い、安全な取り扱いを確保する責任があります。
3. 前処理(破砕・焼却等)
分別後、電池はリサイクル施設で処理されます。リチウムイオン電池の場合、まず冷凍・不活性化した上で破砕し、樹脂や金属筐体、電極粉末に分ける前処理が行われます。一部の揮発成分は焼却され、残渣が出ます。鉛電池なら解体して酸を中和し、鉛を溶解する工程になります。こうした前処理工程も効率と環境負荷の観点で規制のチェック対象となります(最良利用可能技術=BATの適用が求められる)。メーカーは自社電池が適切な前処理法で扱われるよう、信頼できるリサイクル事業者を選定し契約することになります。
4. 資源回収(材料リカバリー)
前処理で得られた金属含有物からコバルト、ニッケル、リチウム、銅、アルミなどを取り出す湿式製錬(ハイドロメタルジ)や乾式製錬(火法)の工程が行われます。例えばリチウムイオン電池では、正極からコバルト・ニッケルなどを溶出・抽出し、硫酸塩や炭酸塩の形で回収します。負極の銅集電体は溶解して電解採取することもあります。こうしたプロセスの結果、規則で定められた材料回収率(コバルト90%以上等)を達成することが求められます。リサイクル事業者は工程ごとに回収できた重量を計測・記録し、当局へ報告します。メーカーは自社の電池が高効率でリサイクルされるよう、リサイクル事業者との協力や、リサイクルしやすい製品設計(Design for Recycling)を行う責任があります。
5. 再資源の利用
回収された金属資源は精製され、新しい製品の原料として販売・利用されます。特にコバルトやニッケル、リチウムなどは再度バッテリー材料として循環できるよう、電池メーカー自身がリサイクル金属を購入するケースも増えることが予想されます。このように循環の輪を閉じることが最終目標であり、前述の再生材使用義務はその一環です。企業にとって、これらリサイクルプロセスへのコミットメントは大きなチャレンジです。自社の手を離れた製品に対しても責任を持つ必要があり、未知の領域であったリサイクル業界との接点が増えます。特にグローバルに製品を販売する企業は、各販売地域での回収義務に対応しなければなりません。EUでは上述のような高い目標が課されましたが、例えば北米やアジアでも類似の枠組みが今後出てくる可能性があります。EU域内では、電池ごとに「Producer Register(生産者登録)」が義務化され、各メーカーは自社が市場に出した電池の種類や量を報告する仕組みが整えられつつあります。
これにより透明性を確保し、将来的に電池の回収やリサイクルに関する責任の所在が明確化されます。企業はこの登録・報告にも対応し、計画的にリサイクルを進めていくことが肝要です。
3. 電池メーカーの事例
厳しいリサイクル要件が課せられる中で、先進的な取り組みを行っている電池メーカーも登場しています。
Northvolt社 – リサイクルとの一体経営
スウェーデンのNorthvoltは、創業当初からリサイクルを事業戦略の中核に据えています。
同社は電池セル工場「Northvolt Ett」の隣接地に大規模リサイクル工場「Revolt Ett」を建設中で、年間125,000トンもの使用済み電池を処理できる能力を目指しています。
Northvoltは既に2021年に使用済み電池由来のニッケル・マンガン・コバルト100%で新規電池セルを製造することに成功しており、品質もバージン材料と同等であると実証しました。
リサイクル材が実用に耐えることを示した意義は大きく、Northvoltの戦略は、自社内にリサイクル設備を持つことで原材料の循環を完結させ、2030年までに原料の50%をリサイクルから賄うという野心的なものです。
引用元:https://northvolt.com/articles/recycled-battery/
Umicore社 – リサイクル事業者との提携
ベルギーの素材メーカーUmicoreは、大手電池メーカーや自動車メーカーと提携し、使用済みEVバッテリーのリサイクルにおける主要企業となっています。例えば自動車メーカーのBMWやVWはUmicoreと協業契約を結び、自社EVの廃バッテリーを優先的にUmicoreの施設でリサイクル処理し、回収金属を再び自社のバッテリーサプライチェーンに戻すサイクルを構築しています。これによりメーカー側は欧州電池規則上の回収・リサイクル義務を確実に果たせるだけでなく、貴重な金属資源の一部をクローズドループで使い続けることが可能になります。Umicoreはニッケル、コバルト、銅、リチウムの高回収率プロセスを持ち、このような専門業者とWin-Win関係を築くことは規則対応の近道となります。
引用元:https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/12/873dd89a06a01503.html?utm_source=chatgpt.com
国内回収網の整備
日本企業でも動きがあります。
トヨタ自動車は欧州各国でハイブリッド車バッテリーの回収ネットワークを早くから構築し、現在では95%以上の回収率を達成しているとされています。これにより欧州電池規則で求められる水準を既に上回っており、今後EVバッテリーにも展開する方針です。
PanasonicやNECなど電池メーカーも、海外パートナー企業と連携し各地域の拠点でリサイクルループを回す実証プロジェクトに参画しています。例えば、北米のRedwood Materials社と提携して米国でTesla車の使用済み電池からコバルトやニッケルを回収し再利用するといった取り組みです。
こうした先行事例は自社だけで抱え込まず異業種連携で課題解決を図っている点が参考になります。これらの事例から明らかなように、電池リサイクルの課題は技術・コスト・スケールなど多方面に及びます。欧州電池規則は確かに企業に高いハードルを課しますが、それを契機に業界全体でイノベーションが促進され、最終的には「資源が循環する持続可能な電池ビジネスモデル」が確立されることが期待されます。企業は規則遵守だけでなく、こうした新たな潮流を捉えて競争力強化につなげていく視点が重要と言えます。
引用元
欧州委員会:Circular Economy(循環経済)アクションプランhttps://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
欧州環境機関(EEA)
https://www.eea.europa.eu
国際エネルギー機関(IEA)
https://www.iea.org