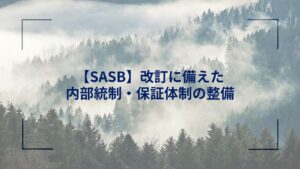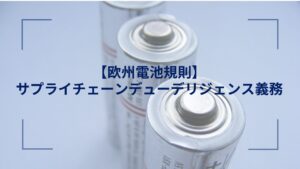欧州電池規則(EU Battery Regulation)は、電池の環境負荷低減と持続可能な資源循環を目的とした法規制です。本規則は、電池のカーボンフットプリント(CFP)の開示義務、人権・環境デューデリジェンス、リサイクル材の使用義務、バッテリーパスポートの導入など、多岐にわたる要件を企業に求めています。本記事では、欧州電池規則の主要要件を整理し、企業が取るべき対応策や今後の施行スケジュール、違反時のリスクについて詳しく解説します。


1. 欧州電池規則の主要要件とは?
欧州電池規則には、多岐にわたる要件が盛り込まれていますが、企業が特に押さえておくべき主要ポイントは環境面での規制強化と持続可能性の確保に関する項目です。本章では、その全貌を概観し、各要件の概要と企業への影響を説明します。欧州電池規則の主な要求事項は、大きく以下の4つに整理できます。
欧州電池規則の要求事項
カーボンフットプリント(CFP)の算定・報告義務
電池製品のライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を評価・申告すること
人権・環境デューデリジェンス(DD)の義務化
原材料調達における人権侵害や環境破壊リスクを調査・公表し、必要な対策を講じること
リサイクル材料の最低使用率の義務化
コバルトやリチウム等の特定物質について、一定割合以上をリサイクル由来資源で賄うこと
製品情報のデジタル登録(バッテリーパスポート)の導入
電池に関する詳細情報をデジタルデータベースに登録し、QRコード等でアクセス可能にすること
加えて、電池へのラベル表示やQRコード付与の義務化、性能・耐久性に関する最低基準、電池の取り外し容易性など、関連する細則も多数定められています。これら全てが組み合わさることで、電池の設計から廃棄に至るまで包括的な規制網が構築されています。
環境規制とサステナビリティ
欧州電池規則はEUの環境政策目標に直結した内容となっており、電池のライフサイクル全般での環境負荷低減と資源循環の促進がテーマです。
カーボンフットプリント(CFP)規制
電池1つあたりが製造から廃棄に排出するCO₂排出量を見える化し、それを削減していくことが求められます。
具体的には、対象電池ごとにCFPを計算し報告する義務が導入され、将来的には高すぎるCFPの電池は販売することができない。これはEV用バッテリーのように生産時のエネルギー消費が大きい製品ほど影響が大きく、メーカーは再生エネルギー活用や工程改善によってCO₂排出を抑える努力が不可欠になります。リサイクルと循環経済: 電池に使われるレアメタル等の資源を無駄にせず回収・再利用するための措置が強化されています。使用済み電池の回収率目標が引き上げられ(例:ポータブル電池63%/2027年)、各社は販売した電池を回収する責任を負います。
またリサイクル効率(回収した電池からどれだけ有用金属を取り出せたか)にも高い目標値が設定され、リサイクル技術の向上が促されています。さらに、回収した資源を新電池に再び使うリサイクル材料使用義務も導入され、例えば2031年以降はコバルトの16%以上を再生資源で賄う必要があります。
上記から電池業界全体でサーキュラーエコノミー(循環型経済)を実現することが目指されています。
有害物質の管理
環境汚染防止の観点から、水銀やカドミウム、鉛といった有害重金属の使用制限も引き続き規定されています。例えば水銀はすべての電池で実質的に使用禁止となり、鉛やカドミウムも一定濃度以上含む場合は電池にその旨の表示を行う義務があります。これは既存の電池指令にあった規制を強化・拡張したもので、例えばボタン電池中の水銀は以前は微量容認されていましたが新規則では完全禁止となりました。
性能・耐久性要件
環境負荷低減には電池寿命の延長も重要です。本規則では電池の性能(容量や出力)や耐久性(充放電サイクル後の容量維持率など)について最低基準を定め、粗悪で早期に使えなくなるような電池の市場流通を防ぎます。例えば充電式の電池であれば、一定回数のサイクル寿命や残存容量の基準値を満たす必要があり、メーカーは製品設計時に寿命試験データを用意しなければなりません。
取り外し・交換の容易性
小型電子機器に内蔵される電池について、消費者が自分で取り外し・交換可能な構造にすることが義務化されます。これにより、電池切れで機器ごと廃棄されるケースを減らし、電池をリサイクルに回しやすくする狙いです。例えばスマートフォンやタブレットの電池も、将来的にはユーザーが容易に交換できるデザインが求められる方向です。
以上のように、環境規制とサステナビリティの観点から、欧州電池規則は製品デザイン、材料選択、製造プロセス、廃棄後処理に至るまで包括的な要求を課しています。企業はこれらに対応することで、環境負荷低減のみならず製品品質やブランド価値の向上にもつなげることができます。
2. 欧州電池規則において企業が対応すべきポイント
上記の主要要件に対し、企業は具体的にどのような対応策を講じるべきでしょうか。
自社の現状把握と戦略立案
まず、自社製品・事業が規則のどの部分に該当するかを洗い出します。電池そのものを製造しているのか、電池を搭載した製品をEU市場で販売しているのかによって、責任範囲や求められる対応が異なります。例えば、自動車メーカーであればEV用バッテリーに関する要件(CFP算定やパスポート発行、回収計画策定など)に重点を置く必要がありますし、電子機器メーカーであれば内蔵電池の取り外し容易性やポータブル電池の回収ルート確保が課題となります。このように自社への適用範囲を明確化した上で、どの要件に優先的に取り組むべきか戦略を立案します。
組織横断的な体制構築
欧州電池規則対応は一部門で完結できるものではありません。環境・CSR担当部門だけでなく、設計・開発、生産技術、購買、品質保証、法務など多岐にわたる部署の協働が必要です。例えばCFP算定には設計部から部品構成情報を、購買部からサプライヤー情報を、生産部から工場エネルギーデータを集める必要があります。また回収・リサイクルの計画にはマーケティングやアフターサービス部門の協力も不可欠です。そこでプロジェクトチームを横断的に組成し、経営層のコミットメントの下で全社的に規則対応を推進する体制を整える必要があります。
データ収集と管理の強化
規則遵守には様々なデータの収集・管理が求められます。具体例として、CFP算定のための原材料から製造工程までのCO₂排出データ、デューデリジェンスのための調達先における人権・環境リスク情報、リサイクル含有率証明のための新材料・再生材使用比率データ、電池パスポートに記載する性能・構成情報などが挙げられます。これらを効率よく収集するには、サプライヤーに対する情報提供依頼(調査票送付や協力覚書の締結など)や、必要に応じて社内システムの改修(環境データ管理モジュールの追加等)を検討します。情報のトレーサビリティ(追跡可能性)も重視されるため、由来が異なる原材料やリサイクル材が電池のどこに使われたかを後から証明できるような仕組みづくりも求められます。
第三者検証・認証取得の計画
カーボンフットプリントやデューデリジェンス報告は第三者による検証が必要です。対応すべきポイントとして、どの認証機関に依頼するか、いつまでに取得するかの計画を早めに立てることがあります。第三者検証には一定の時間がかかるため、申告期限ギリギリに依頼すると間に合わないリスクがあります。逆算して計画的に審査・検証プロセスを組み込むことが大切です。例えばEV電池のCFP申告が2025年初頭に必要なら、2024年中頃にはデータ算定を終え検証機関に審査を依頼する、といったタイムライン管理が求められます。
EU当局や業界団体との情報共有
規則の詳細運用については今後も変更や追加ガイダンスがあります。欧州委員会からの公式発表や各国当局の指針を継続的にモニタリングする必要があります。また、自動車や電池業界の団体に加盟し、他社の取り組み事例や当局との対話に関する情報を収集することも有益です。特に難解な要件(例:ライフサイクル算定手法)については、欧州の専門コンサルタントの知見を借りることも検討すべきです。
罰則や規制の施行スケジュール
欧州電池規則の施行スケジュールは段階的かつ長期にわたります。また、各要件に違反した場合のペナルティも企業リスクとして把握しておく必要があります。以下に主要なマイルストーンとペナルティの概略を示します。
3. 欧州電池規則の施行スケジュール
2024年2月18日
規則の基本条項が適用開始(欧州電池規則発効)。
この時点で新規則がEU内で法的効力を持ち、一部の一般義務(例えば禁止物質の規制など)が有効になります。
2025年2月18日
電気自動車用電池に対するカーボンフットプリント(CFP)申告の義務化開始。
メーカーは対象電池について第三者検証済みのCFP宣言書を準備しなければEU市場販売ができなくなります。
※2024年2月18日までに関連する委任規則や実施規則が採択された場合、その施行後12カ月後に適用されるとされています。
2025年8月18日
サプライチェーン・デューデリジェンス(DD)の義務開始。
コバルトなど指定原材料の責任ある調達に関するデューデリジェンス体制が求められ、DD報告の第三者検証や当局提出が必要になります。同時に旧電池指令の大部分が廃止され、本規則へ完全移行。
2026年8月18日
電池のラベル表示義務の全面施行期限。
欧州委員会が策定する統一ラベル仕様に基づき、すべての対象電池に規定項目を記載したラベル貼付が必要になります(※実施法公布の時期によっては多少前後する可能性あり)。
2027年1月1日
使用済み電池からの素材回収率目標の第一段階達成期限(例:リチウム50%)。
リサイクル事業者がこの時点までに規定のリサイクル効率を達成する必要があり、達成状況を評価する年です。
2027年2月18日
デジタル電池パスポート制度の施行開始。
EV用・LMT用・大型産業用電池に対し、電子的なバッテリーパスポートへの情報登録と、それにアクセス可能なQRコード表示が義務化されます。
2027年12月31日
ポータブル電池の回収率目標63%達成期限。
加盟国レベルで回収率を評価し、未達の場合追加措置が検討されます。
2028年2月18日
カーボンフットプリントの上限値規制施行。
設定された最大CFP値を超える電池は以後EU市場に投入不可となります。実際の上限値は事前に委任法で公表され、企業は直前までに製造プロセスを調整しておく必要があります。
2028年8月18日
リサイクル材含有率の情報開示義務開始。
対象電池について、コバルト・リチウム等の再生資源使用比率を年度別・工場別に算出し、技術文書に記載する義務が生じます。
2028年12月31日
LMT用電池の回収率目標51%達成期限。
2030年12月31日
ポータブル電池の回収率目標73%達成期限、LMT用61%達成期限。
2031年8月18日
リサイクル材最低含有率の義務化開始。
対象電池の活性材料中に、コバルト16%、鉛85%、リチウム6%、ニッケル6%以上のリサイクル材を含めることが法的に要求され、この証明が求められます。
2033年以降
電池性能・耐久性やその他要件の見直し時期。
技術進歩に応じ、さらなる基準強化や新規項目追加が検討される可能性があります。またコバルトの含有率目標が26%に引き上げ(2035年予定)など、長期的な目標も控えています。
4. 欧州電池規則の罰則規定と企業リスク
欧州電池規則自体には細かな罰則金額は明記されておらず、各加盟国が違反時のペナルティを定めることになります。ただし、一般的にEUの製品環境規制違反には以下のような措置が想定されます。
市場アクセスの禁止
規則を満たさない電池製品はEU域内で販売できません。例えばCFP宣言未提出の電池や、リサイクル含有率証明のない電池は税関で差し止められたり、リコールを命じられる可能性があります。
行政罰(罰金)
違反の重大性に応じて高額な罰金が科される場合があります。EU各国は企業に対し「効果的かつ抑止力のある制裁」を課すよう求められており、故意または重大な過失による違反には数万〜数十万ユーロ規模の罰金となるケースも考えられます(詳細は各国法令で規定)。
是正命令と公表
規制当局は違反企業に対し是正計画の提出と実施を求めるほか、違反事実を公表して社会的制裁を与える場合もあります。企業名が公に公表されれば信用失墜や取引停止といった間接的ダメージも避けられません。
刑事罰の可能性
一部悪質なケースでは、関与した経営者個人に対する刑事罰(例えば虚偽申告による詐欺罪等)が追及される可能性もゼロではありません。
このように、欧州電池規則は厳格なスケジュール管理とコンプライアンス対応を企業に要求し、怠れば市場喪失や財務・信用面で大きなリスクを招きます。企業としては年次のマイルストーンを逆算して準備を進めるとともに、常に法令順守状況をレビューし、問題があれば早期に対処する姿勢が重要です
引用元
Regulation (EU) 2023/1542(正式文書全文)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542
欧州委員会:バッテリー・蓄電池に関する解説ページ
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries-and-accumulators_en
Proposal for a Regulation on batteries(COM/2020/798)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
旧バッテリー指令(Directive 2006/66/EC)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066