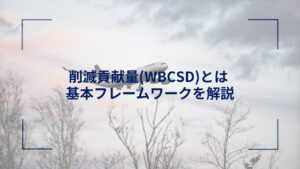SASB(サステナビリティ会計基準審議会)は、企業のサステナビリティ情報開示基準を策定する国際的な組織です。主に投資家向けに財務的に重要なESG指標を業種別に定めており、その基準(SASBスタンダード)は世界の多くの企業で採用が拡大しています。本記事では、SASBの設立背景や目的、基準の仕組み、他の基準との違い、そして企業にとっての意味合いについて、全体像を解説します。


1.SASBの概要と設立背景
SASBとは「Sustainability Accounting Standards Board」の略称で、2011年に米国で設立された非営利団体です。その目的は、企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する情報開示の質を高め、中長期的視点を持つ投資家の意思決定に資することにあります。具体的には、業種ごとに財務パフォーマンスへ影響し得る重要なサステナビリティ課題を特定し、開示すべき指標や項目を標準化する「SASBスタンダード」を策定しています。こうした業種別基準により、企業は自社の事業に関連するESG情報を的確に開示でき、投資家は企業間で比較可能なデータを得られるようになります。
SASBの構造
SASBは2018年に11セクター・77業種分のスタンダードを完成させ、公表しました。各業種ごとのスタンダードは、「Disclosure Topics(開示トピック)」「Accounting Metrics(定量指標)」「Technical Protocols(算定方法の手引)」「Activity Metrics(活動量指標)」で構成されており、企業がどのESG項目についてどのようなデータを報告すべきかが詳細に示されています。例えばエネルギー業界と金融業界では直面する課題が異なるため、それぞれに適した指標セットが設けられています。このように業種特有の基準を定め、企業の長期的リスク・機会を財務的観点から評価しやすくするのがSASBスタンダードの特徴です。
2.他の開示基準との関係(ISSB統合とGRIとの違い)
SASBは2021年に国際統合報告評議会(IIRC)と統合してValue Reporting Foundation(VRF)となり、翌2022年にVRFごとIFRS財団に吸収されました。現在はIFRS財団の下で設立された国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がSASB基準の維持・改訂を引き継いでいます。ISSBはグローバルなサステナビリティ開示基準の策定を担い、SASBスタンダードを土台として各業種の開示要求をまとめる方針です。実際、ISSBが2023年に公表した最初の基準「IFRS S1一般要求事項」では、企業に対しISSB基準を適用する際に関連するSASBスタンダードを参照し適用可能性を検討することが求められています。つまり今後、SASBスタンダードはISSB基準(国際サステナビリティ開示基準)の一部として組み込まれ、各国で公式に採用される見通しです。実際にISSB基準は既に約40の法域で採用・参照され始めており、SASBスタンダードもこれに伴い世界的な適用が進むと期待されています。
GRIとの違い
ESG情報開示のもう一つの代表的枠組みにGRIスタンダード(Global Reporting Initiative)があります。SASBとGRIは一見似ていますが、目的と対象読者が大きく異なります。SASBが主に投資家を対象とし、財務に与える影響が大きい情報(シングルマテリアリティ)に焦点を当てるのに対し、GRIは投資家以外の消費者や市民社会など幅広いステークホルダーも対象とし、企業の環境・社会への影響を包括的に報告することを重視します。平たく言えば、SASBは「財務に直結するサステナビリティ情報」を、GRIは「社会的影響も含めた広範なサステナビリティ情報」を扱う基準と言えます。そのため、SASBでは各業種あたり20~30程度の厳選された定量指標が提示されますが、GRIでは汎用的かつ定性面も含む200項目近い開示事項があります。両者はともに企業の透明性向上に資する点で共通していますが、企業は投資家向けの財務材料を強調するならSASB、幅広い社会への説明責任を果たすならGRIといった具合に目的に応じ使い分ける必要があります。近年はISSBがSASB基準と他基準の相互運用性確保にも注力しており、将来的には両者の併用がより容易になることが期待されます。
3.SASBスタンダードの活用状況と企業への示唆
SASBスタンダードは年々国際的な普及が進んでいます。2024年現在、世界では2,500社以上(70超の国・地域)がSASB基準を採用しているとの報告もあり、特に大型株での採用率が高まっています。
実際、S&Pグローバル1200指数構成企業のうち906社がSASBを採用し、日本企業でもTOPIX100の51社が採用しています。トヨタ自動車、東芝、三菱地所といった大企業がSASB基準に沿ったサステナビリティ報告書を発行し、温室効果ガス排出量や水使用量、労働安全等のデータを開示しています。これら企業は、SASBスタンダードに従うことで投資家に対して財務的に重要な情報を明確に示し、国際的な比較可能性と自社の信頼性向上を図っています。
SASBのメリット
SASB基準を活用するメリットとして、企業側には
(1)開示情報の比較可能性と信頼性が高まること
(2)ESGリスク管理の枠組みが得られ経営の長期的安定に寄与すること
(3)資本市場での評価向上により資金調達が有利になる可能性があること
などが指摘されています。社会側にとっても、企業間で統一された指標により透明性が増し、持続可能な社会への移行が促進されるという利点があります。
今後、日本でも金融庁のサステナビリティ開示基準(SSBJ)がISSB基準に沿って策定される予定であり、その中でSASBスタンダードへの言及が盛り込まれる見込みです。したがって企業のサステナビリティ推進担当者は、SASB基準の内容と自社業種の該当指標を把握し、自社の開示とのギャップを確認しておく必要があります。特に投資家視点で重要なKPI(例えば温室効果ガス排出量、労働災害率、水リスクなど)については、SASB基準に従ったデータ収集・管理プロセスを整備することが求められます。SASBスタンダードは法的強制力はないものの事実上のグローバル標準となりつつあるため、日本企業もこれを活用することで国際的な評価に耐えうるサステナビリティ情報開示を実現できるでしょう。
4.SASBまとめ
最後にまとめると、SASBとは何かを一言で言えば「業種別の財務に重要なサステナビリティ情報を標準化する国際基準」です。GRIやTCFDなど他の枠組みと併存しつつも、ISSBによる基準統合の流れの中で中心的な役割を果たす存在となっています。企業のサステナビリティ担当者にとって、SASBスタンダードの理解と活用は、投資家との建設的な対話やグローバルでの評価向上の鍵となるでしょう。
引用先
【IFRS財団】 「ISSB proposes comprehensive review of priority SASB Standards…」
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2025/07/issb-comprehensive-review-sasb/
【JPX ESG Knowledge Hub】「ESG情報開示枠組みの紹介:SASBスタンダード」
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/disclosure-framework/03.html