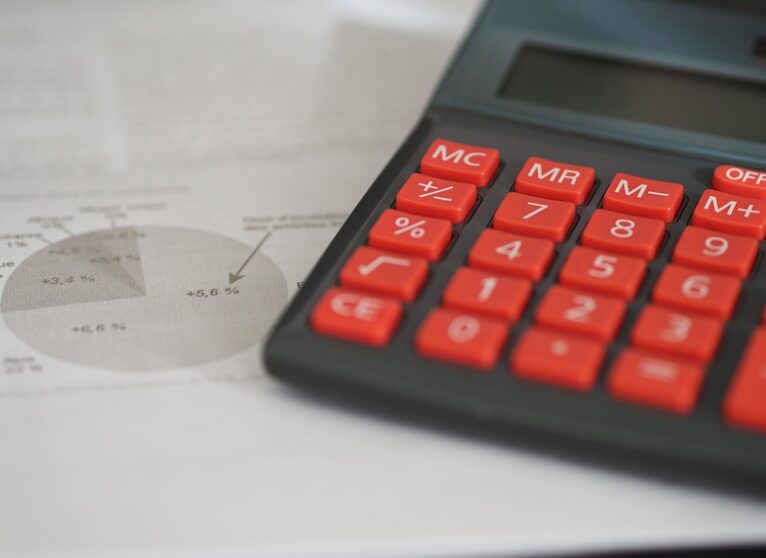概要と重要性
初めて第三者保証を受ける企業様や、新たな報告基準への対応を控えている企業様向けに、正式な第三者保証の前段階でプレ審査を行います。第三者保証に備え、現状のデータ算定や開示体制が要求基準に照らしてどの程度整っているかをを評価し、不足している対応や是正すべき点を明確化します。本番の保証に向けた事前リハーサルであり、事前準備を万全にすることで本審査(第三者保証)をスムーズに進めることが可能となります。
当社のプレ審査では、第三者保証までに対処すべき課題を洗い出し、効果的な改善計画策定を実施いたします。訪問の有無や範囲も含め、お客様のニーズに応じて柔軟に実施内容をカスタマイズ可能です。
また削減目標を掲げる上で、自社の温室効果ガス排出量を正しく把握・管理し、その削減努力を裏付けることは重要な経営課題です。第三者による排出量検証は、開示情報を透明かつ信頼性の高い形で示す手段であり、グリーンウォッシュへの批判を避ける上でも有効です。また国際標準や算定プロトコルが改訂された場合、現行システムの見直しが必要になってしまいます。こうした状況で、事前に専門家の視点で現状評価を受けておくことは多くの利点をもたらします。
範囲と対象
当社の第三者保証は、以下のような幅広いテーマを対象としています。

組織レベルの温室効果ガス排出量のプレ審査
Scope 1,2,3 のバウンダリが適切か、排出源が網羅されているか、排出係数や活動量データが一貫して管理されているかを中心に診断しリスク要因を洗い出します。

サステナビリティ/統合報告書のプレ審査
サステナビリティ報告書や統合報告書に掲載予定の環境・社会・ガバナンスデータについて、その集計・算定・各種開示と保証基準との整合性を評価します。

製品レベルの温室効果ガス排出量に関するプレ審査
カーボンフットプリント集計・算定が ISO 14067 や関連指針に適合しているか、また妥当性と再現性が確保されているかを審査します。
当社におけるプレ審査の特徴
プレ審査の実施時期や範囲、工数はお客様のニーズに応じて調整可能です。「短期間で主要なポイントだけチェックしてほしい」「初年度は徹底的に見てもらいたい」など、ご希望に沿った進め方で対応いたします。
当社の検証人は温室効果ガス検証やサステナビリティ報告の実務に精通したプロフェッショナルです。過去多数の企業の検証を主導してきた知見を活かし、陥りがちなミスや注意点を的確に指摘します。
単に現状を評価するだけでなく、改善に向けた具体的なアドバイスまで踏み込んで提案いたします。報告書には必要に応じて対応策の優先順位づけや推奨スケジュールも盛り込みます。
プレ審査から本番の第三者保証業務まで一貫して当社が担当することで、二重手間なくスムーズに移行できます。なお第三者保証審査時には、プレ審査を担当した検証員とは別の検証人が本審査でリードを務めます。
プレ審査の進め方
当社ではお客様の状況に合わせ、柔軟にプレ審査の内容を設計いたします。一般的な実施内容の一例は以下の通りです。
最初にお客様の事業内容、組織体制、温室効果ガス排出源やデータ収集フロー等についてヒアリングします。これにより、プレ審査を効果的に行うための計画を立案します。必要に応じて事前に基本資料のご提供をお願いし、検証人が分析を行います。
提供いただいた算定ルールや算定結果の報告書、エビデンス資料をもとに、基準との適合状況をチェックします。例えば、GHG算定ならISO 14064やGHGプロトコルの要求事項に照らし、現行の方法で満たされている点・不足している点を整理します。
ご要望に応じ、実際の事業所や施設を訪問しての予備審査を実施します。データ算定プロセスの現場確認や、担当者への追加ヒアリングを行い、書類上では見えにくい運用面のギャップも洗い出します。初回は訪問無しで書類中心に行い、必要に応じ次年度以降に現地確認するなど段階的な対応も可能です。
プレ審査の結果判明したギャップや改善ポイントについて、報告書を作成しご提示します。特に修正が必要と判断された事項については優先度や対応案も含めて整理いたします。報告ミーティングにて検証員から直接ご説明し、ご質問にもお答えします。
プレ審査を受ける利点
- 不足対応の早期発見
プレ審査を通じて、第三者保証本番までに何を準備・改善すべきかが明確になります。例えば排出量算定方法の抜け漏れやデータ記録の不備など、事前に改善可能な指摘事項を早期に把握できます。本番前に対策を講じることで、検証時の指摘事項や追加対応の発生を最小限に抑えることができます。 - 要求事項の理解深化
専門の検証員がヒアリングや書類確認を行う中で、国際規格やガイドラインの求めるポイントを解説します。これにより担当者の規格理解が深まり、自社の取り組み水準が基準に照らしてどのレベルにあるか把握できます。単なるチェックに留まらず社内の知識蓄積にもつながります。 - 現実的な改善計画の策定
ギャップ分析の結果として判明した不足部分に対し、優先順位を付けて対処するためのロードマップ作成を実施します。例えば来期の検証に向けて半年以内に整備すべき事項、長期的課題などを整理し、社内で合意形成しやすい改善計画策定をお手伝いします。これにより認証・保証取得までの具体的なタイムスケジュールを描くことが可能です。 - 社内意識の醸成
初めて検証を受ける場合、社内の関係者にとって何をどこまで準備する必要があるか見通せないことがあります。プレ審査を経験することで、経営層から現場担当者まで第三者保証への意識が高まり、社内体制整備の機運が高まります。本番の検証に向けた社内横断的な協力体制づくりにも寄与します。